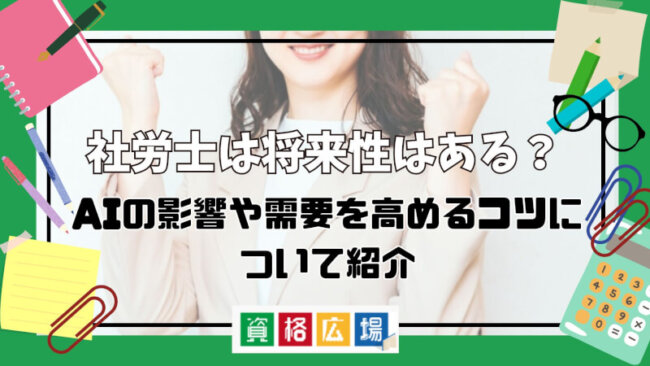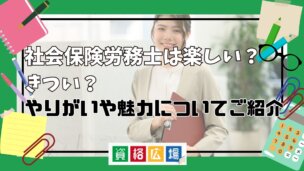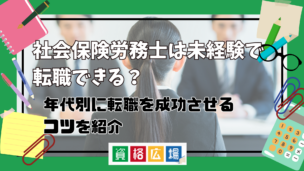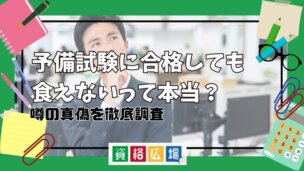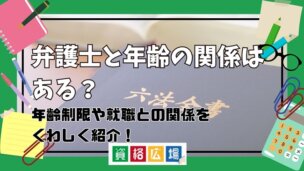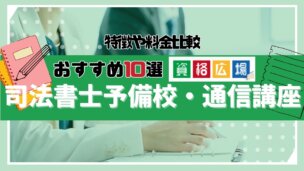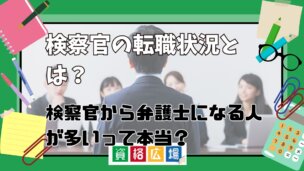社労士とは主に労働や社会保険に関する手続きや相談などを行う仕事です。
企業からのニーズが高い仕事であるもののAI技術の発展により影響を受ける可能性が高く、一部では「将来性がない」と言われることもあります。
しかし社労士は合格率6~7%程度の難関国家資格であり、専門性の高さや独占業務があることなどを踏まえると将来性はあるといえます。
そこで今回は社労士の将来性やAIによる影響、需要を高めるコツなどについて紹介します。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
社労士に将来性はある?

社労士は専門性や希少性が高い仕事であることから、日本の雇用制度や社会保険制度が存続する限りなくなることはなく、将来性については心配する必要はないでしょう。
社労士にしかできない独占業務がある
社労士の独占業務は社会保険労務士法に基づき、以下の社労士の資格を持たない者がこれらの業務を行うことは法律違反となります。
- 1号業務…行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類の作成(第2条第1項第1号)
- 2号業務…労働者名簿、賃金台帳、就業規則等の(行政機関への提出を目的に作成するわけではない)書類の作成(第2条第1項第2号)
働き方の多様化に伴い、企業が直面する人材や労働に関する課題も変わっていきます。
つまり企業が存続し従業員を雇用する限り、社労士の仕事はなくなることがありません。
また社労士は年金に関する専門家でもあります。
なかには事業主に代わって帳簿を作成したり、総務部の業務を担ったりするため、雇用に関する深い知識が必要とされる職務です。
高齢化社会や年金制度の変化により、今後は年金に関連する業務の代行もさらに増えることが予想されます。
個人からの相談業務も増える見込み
社労士の資格を持っていれば法律や制度に関する専門的な知識を活かせるため、個人からの相談業務に対応することもできます。
たとえば年金申請の代行や保険に関する相談、 職場に関する悩みや労働に関する相談を受け付けており、必要に応じて企業との交渉などを行うケースも。
特に個人の場合、専門的な知識がないと判断が難しい障害年金の申請など、社労士に依頼するケースが増えてきています。
以上のことから社労士の仕事は企業・個人からの需要が高く、将来性があ仕事であるといえるでしょう。
社会保険労務士(社労士)試験の難易度は高い?試験内容・勉強法や他資格とのランキング比較まで解説
社労士に将来性がないと言われる理由とは?社労士の仕事とAIによる影響

最近ではAIの普及による業務効率化が仕事を奪うといった声もささやかれていますが、社労士の場合はどうなのでしょうか。
ここでは、社労士の仕事内容とAIによる影響を受ける可能性について紹介します。
1号業務(手続代行業務)
社労士の仕事のひとつである1号業務とは労働社会保険に関する法令に基づいて申請書類を作成し、それを労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)、年金事務所などの行政機関に提出する業務のことを指します。
この業務は社労士法により独占業務とされており、無資格者が業として行うと法律違反となります。
1号業務はAIによる代替が懸念されている分野ですが、現行の法律では完全な自動化は難しく、社労士の業務から消失する可能性は低いと考えられます。
理由としては法令の解釈や個別のケースに応じた判断が求められる場合に、AIが必ずしも柔軟に対応できないことがあるためです。
特に複雑な事例や異常な状況の場合は社労士の専門的な知識と経験が不可欠であり、AIはデータに基づく対応に限られるため難しいといえるでしょう。
さらに、AIが書類を自動的に作成できたとしても、その内容に関する最終的な法的責任は人間が負う必要があります。
2号業務(帳簿作成業務)
社労士の2号業務は労働社会保険に関する法令に基づいて帳簿や書類を作成し、賃金台帳の作成を請け負うことを指します。
帳簿には主に「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」「年次有給休暇取得管理簿」の4種類があり、これらは労働基準法により企業に作成が義務付けられています。
また、就業規則や各種労使協定の作成も2号業務に含まれます。
就業規則は経営者自身が作成することもできるものの、法律に抵触していないかや労働者への配慮がなされているかを慎重に確認する必要があります。
AIはこれらの帳簿の作成や更新を迅速に行うことができますが、内容の正確性や法的適合性を確保するためには社労士の確認が不可欠です。
特に、法改正が頻繁に行われる日本の労働法制の場合、AIだけでは最新の規則に対応することが難しいため社労士はなくてはならない存在です。
3号業務(コンサルティング業務)
社労士の3号業務は労務管理や社会保険に関する相談、助言、コンサルティングなどを指します。
3号の業務は1号から3号の中でもAIによる代替が最も難しく、将来的にも重要な役割を果たすと考えられています。
理由としては3号は企業の労務管理や働き方改革、ハラスメント対策などの領域では、企業や従業員の個別の状況を考慮した柔軟な提案が求められるからです。
AIはデータ提供には優れているものの、企業文化や従業員の特性に応じた具体的な改善策を提案するには不十分な面があります。
生身の社労士が現場の状況を理解しながら提供するコンサルティング業務は企業の成長を支えるために不可欠なサービスであり、今後も需要が高まる業務であると言えるでしょう。
紛争解決手続代理業務
社労士のなかでも「特定社労士」という資格を持つ人の場合、通常の社労士の業務に加えて紛争解決手続代理業務と呼ばれる業務を担当することが出来ます。
紛争解決手続代理業務とは企業と従業員の間で発生したトラブルに対し、特別な資格を持つ社労士(特定社労士)が当事者の代理として裁判外で問題解決を支援する独占業務です。
紛争解決手続業務は将来的にもAIが担うことが難しいと考えられています。
特定社労士が紛争解決のための事前調査や解決策の検討にAIを活用することはできますが、調停やあっせんの場においては人間以外が参加することはできないからです。
労働トラブルは感情的な要素が強い傾向にあり、当事者間の交渉には共感力や調整能力が求められます。
AIが提供するデータ分析や法的アドバイスは補助的な役割に過ぎず、実際の交渉や説得は人である社労士が果たすべき仕事なのです。
特定社労士試験の難易度は高い?他資格とのランキング比較や合格率・偏差値・勉強時間の目安について解説
社労士として需要を高めるには
先にも述べたように、社労士の仕事は企業や個人からのニーズが高いことが分かりました。
しかし社労士の資格を持っているからと言って、絶対に安心というわけではありません。
ここでは、社労士として需要を高める方法について紹介します。
社労士としての専門性を高める
社労士としての専門性を上げることで特定の分野において支援を求める企業や個人からの相談が増得る可能性が高くなります。
基本的な知識を習得するだけでなく、自身の得意分野を確立するのがおすすめです。
具体的には社会保険や年金制度は不定期に改正されるため、定期的に知識を更新していくなどが挙げられます。
最新の情報を取り入れ、特定の分野で自分の強みを効果的にアピールすることで、依頼者や企業からの信用度が上がるはずです。
ダブルライセンスを取得する
ダブルライセンスを取得することで社労士の独占業務にとどまらず、さまざまな業務に対応できるようになります。
たとえば申請代行を独占業務とする資格には、行政書士や司法書士が挙げられます。
複数の書類作成や手続き代行ができるようになると、依頼者は一括して手続きを行えるためリピート率が高くなります。
またコンサルティング業務に特化したいのであれば中小企業診断士の資格を、個人向けの相談を主に行うのであればFP技能士の資格もおすすめです。
資格によっては社労士の資格取得で学んだ内容をいかせることもありますし、社労士という難関資格を取得していれば比較的合格率の高いものだと取得しやすいでしょう。
どの分野で活躍したいかは人によって異なるので、ある程度社労士としての経験を積んで余裕のある方はぜひダブルライセンスにチャレンジしてみてください。
宅建と社労士どっちが難易度高い?ダブルライセンスのメリットも紹介
社労士になるには

社会保険労務士になるためには、まず社会保険労務士試験に合格し、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録する必要があります。
社会保険労務士試験は毎年8月中旬に行われ、合格発表は11月に行われます。
受験資格についてまとめると以下の通りになりますが、たくさんあるので気になる方は全国社会保険労務士会連合会のサイトをチェックすることをおすすめします。
| 社会保険労務士の受験資格 | 詳細 |
|---|---|
| 学歴 | 大学や短大等を卒業した者 |
| 3年以上の実務経験 | 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員又は従業者として従事した期間が3年以上になる者 |
| 特定の国家試験合格 | 行政書士試験を合格した者や、税理士試験を合格した者 |
登録の条件として2年以上の実務経験があるもしくは事務指定講習を修了していることが条件です。
講習を修了した後に登録を行いますが、開業または勤務の形態によって登録の種類や料金が異なります。
全国社会保険労務士連合会および都道府県社会保険労務士会に加入して登録が完了すれば、社労士としての業務を開始することができます。
社労士の年収
厚生労働省のデータによると、社労士の平均年収は947.6万円となっています。
全職種を含めた平均年収は400万円程度なので、社労士はかなり高い水準にあると言えるでしょう。
また社労士は働き方によっても収入が変わり、独立して自分の事務所を立ち上げたりフリーランスとして働くことでさらなる年収アップも狙えます。
士業は男性が多いイメージである者の、社労士は難関資格の国家資格であることから他の資格と比べ活躍している女性が多い傾向にあります。
したがって、ライフスタイルが変わって子育てとも両立がしやすく、女性にとってキャリアの選択肢のひとつだといえるでしょう。
社労士試験ならアガルート!

引用:アガルート公式サイト
アガルートは難関資格試験に強い大手通信講座です。
試験に合格することを目的とした無駄のない講座が特徴で、2024年の社労士試験では、合格率が全国平均5.19倍(6.9倍)の35.82%と高い合格実績数を誇ります。
期間限定のアウトレットセールや最大20%OFFになる割引制度もあり、お得に受講できるメリットもあります。
公式サイトから簡単に無料資料請求ができるので、気になる方は下のリンクから確認してみてください。
社労士の仕事は将来性がある
今回は社労士の将来性やAIによる影響、需要を高めるコツなどについて紹介してきました。
資格が役に立たないという事実はなく、むしろ働き方改革の取り組みが活発に行われる中、社会保険労務士の企業コンサルティングにおけるニーズが高まっています。
一方で、従来主流であった労務の書類作成業務はAIやIT化の影響を受けて一部の業務が省略されることも予想されます。
しかし社労士の資格を取っても個人での努力や向上心は必要です。
自分の得意分野の専門性を高めたり、ダブルライセンスの取得によって業務の幅を広げるなどが求められます。
今回ご紹介した将来的に需要が高まる分野を極めて、社会のニーズに応えることができる社労士をめざしてみてください。