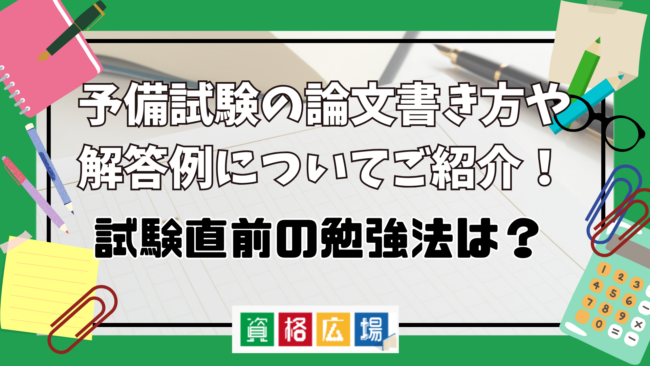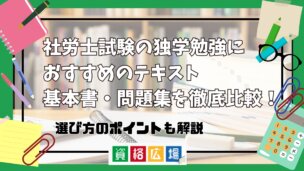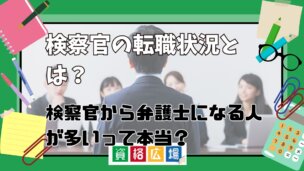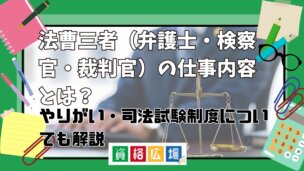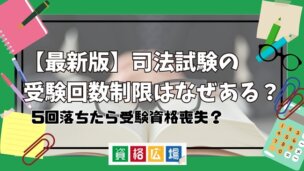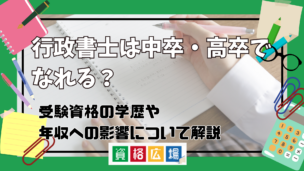司法試験を受験するにあたって、受験資格を得るために近年法科大学院ではなく予備試験を利用する方が増えています。
予備試験において、一つの壁と言われているのが論文式試験で、特に未経験者の方には大きな障害となるでしょう。
そこでこの記事では、最難関とされる予備試験の論文について書き方や試験直前の勉強法をご紹介し、書けない方に向けた解答例や論法などについて解説していきます。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
司法試験予備試験合格におすすめの通信講座
予備試験の論文式は最難関!?
まず最初に、予備試験の論文式の難易度が高いとされている理由や、論文式試験の合格率などをご紹介します。
脅かすわけではありませんが、難易度が非常に高いことを理解し、勉強のモチベーションに繋げてみて下さい。
予備試験の論文式の難易度が高いとされている理由
論文式試験の難易度が高い理由は様々ですが、最も厳しいのは自分で論点を発見し、論証まで持っていく流れを構築しなければならない点です。
「与えられた問題に答える」というアウトプットをするだけでは手も足も出ず、最初から最後まで思考力を試されることになります。
さらに、最後に示した論証結果が曖昧な物になってしまうと評価も低くなるため、筋道をしっかり立てた上ではっきりとした結論が必要になります。
そしてその筋道の立て方もある程度の型が決まっており、論述練習の前にまず型を構築できるようになる必要があります。
他にも試験時間が足りなくなったり、試験自体が2日間に渡るため体力的にも集中力的にもきついなどの理由も挙げられています。
論文式試験の合格率は?
以下に過去5年間の論文式試験の合格率を示します。
| 年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,562 | 487 | 19% |
| 2022 | 2,695 | 481 | 17.8% |
| 2021 | 2,619 | 479 | 18.2% |
| 2020 | 2,439 | 464 | 19.0% |
| 2019 | 2,580 | 494 | 19.1% |
この受験者数は短答試験の合格者からご紹介しています。
予備試験の論文試験の受験者数は増加傾向にあり、中でも昨年は受験者数が最も多かった年になりました。
とはいえ、例年の合格率を見て行くと、例年20%を少し下回るくらいになっており、難易度が非常に高いことが分かります。
書き方における「三段論法」
初心者の方は最初論文をどう書き始めれば良いのかという部分から迷うことになりますが、一般的に三段論法というやり方が予備試験の論文試験の解き方とされています。
これが身についていないと過去問の練習すら始めることができません。
三段論法とは?
予備試験における三段論法とは、「規範」「あてはめ」「結論」の三段階に分けて論述する方法です。
元々は、「大前提」「小前提」「結論」を組み立てて推論をする方式です。
大前提とは、一般的なルールや変えられない原理を指し、小前提は今目の前にある事実を指し、その2つから結論を導きます。
実際に軽く例を出すと以下のようになります。
- 大前提:王様は国の中で最も偉い人である
- 小前提:ジョンは王様である
- 結論:つまり、ジョンは国の中で最も偉い人である
この論述方式を予備試験でも応用していきます。
規範とは?
規範とは先ほどご紹介した大前提にあたる部分で、論文試験では参考条文がこれに当てはまることが多くなります。
また、条文をそのまま規範とするだけではなく、問題文から得られた状況の説明と合わせて解釈したもの(条文をもう少しかみ砕いたもの)でも規範として扱うことができます。
当てはめとは?
あてはめは、規範に問題文中の出来事をひたすらあてはめていく作業のことです。
規範とは別の作業として定義していますが、規範を考えている時点で何がどこに当てはまりそうかある程度考えて行けるようになることが重要です。
結論
結論は、あてはめまでを行った結果が規範に沿う事実なのかどうかで肯定・否定を結論付けます。
結論を意識しながらでなければ、論述することは難しいため最初になんとなく、肯定か否定かどちらで結論付けるか考えておくようにしましょう。
司法予備試験論文式の答案構成の書き方
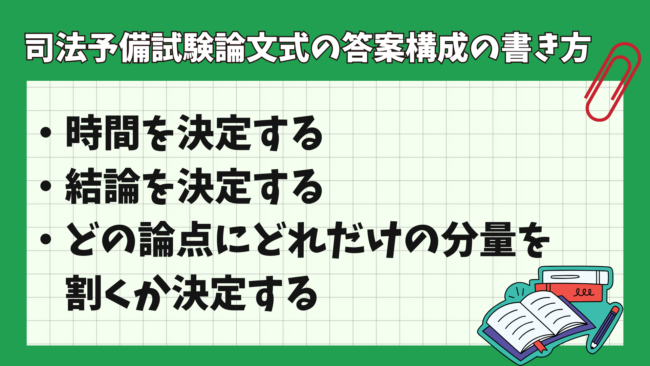
ここからは、論文式の答案構成の書き方を解説していきます。
論理的に思考し、説明ができたとしても答案に上手く落とし込み、記述することが出来なければ点数にはなりません。
試験開始から10分ほどで全体的にどう論述するかという構成を立てていくことになります。
普段の勉強から正しい答案構成を練習しておくことで、本番の時間的なペース配分などを乱すことなく回答することができます。
時間を決定する
予備試験の1科目当たりの時間は単純計算で70分となっており、決して長くはなく、時間が足りないという方が多くいらっしゃいます。
そんな中、答案構成に何十分も割いていては、確実に最後まで解くことができません。
そこで、普段の勉強時点から「答案構成は最初の何分まで」と決めておき、その時間内に答案構成を完了できるように勉強を進めておきましょう。
一般的には10分程、長い人でも15分程で答案構成を終えているようです。
結論を決定する
次に答案構成を作成する上で重要なのが、結論を先に決定することです。
結論を先に決定していないと、結論にたどり着くまでに論述が迷走してしまう可能性があります。
この論文式試験では、受験者の論理的思考力を試しているため、迷走した解答は非常に低評価になりやすく、白紙の次に避けたい解答になります。
逆に、結論を先に決めることができれば、必要な情報と不必要な情報を見極めやすくなりますし、整理された論述を展開することができるようになります。
どの論点にどれだけの分量を割くか決定する
論文式試験では、1問につき複数の論点を自分で書き出し、それについて論述することになります。
しかし、全ての論点が同じだけの重要度を持つわけではないため、重点を置くべき論点、触れておくだけで良い論点などを分けていかなくてはなりません。
具体的には、論点を洗い出した後に、「どの論点にどれだけの項目数を当てるか」を決定していきます。
項目も1,2,3といった番号のみではなく、1の中でも分かれたりしますし、その書き方もある程度決まっていることに注意しましょう。
これを答案構成の時点で行っておくことで、最終的に分量バランスの良い答案を完成させることができます。
論文式対策における解答例の上手な使い方
こういった試験対策では過去問を利用した勉強法が主流な訳ですが、論文式試験では解答例をそのまま暗記しても意味はありません。
ここからは、論文式試験の解答例をどう扱って勉強すればよいのかを解説していきます。
三段論法が正しく扱えているかを確認する
論文式試験の解答例はあくまで1例であって、それが全てではなく、解答例と違っても正しく解答出来ている可能性はあります。
そこで、解答例を使用して確認すべきはまず三段論法についてです。
解答例を見ながら規範をどのように決定し、どのように事実をあてはめて、結論にどうやって繋げているのかを確認しましょう。
答案構成が出来ているか確認する
三段論法を確認した後は、答案構成について確認していきましょう。
解答例から答案構成を自分で作成し、自分の解答に使用した答案構成を見比べ、論点の数は少なすぎないか、各論点に対する論述量は適切かなど細かく見てみて下さい。
言い回しを覚えていく
せっかく答案構成や三段論法が出来ているのに、言葉の言い回しや結論の出し方で減点されることもあります。
言い回しや結論の導き方は論述式の数少ない暗記分野になるため、同じ内容でも解答例やテキストと言い回しが違う場合は修正していくようにしましょう。
また、どのような言い回しが得点化されやすいのかポイントを抑えるように知識を深めるとよいです。
司法予備試験論文式の勉強方法
先ほどは答案例の使い方をご紹介しましたが、ここからは論文式試験の全体的な勉強方法をご紹介していきます。
最初から上手くはいかないので、段階的に学習を進めていきましょう。
時間制限をせず、型を作る練習から始める
論文式が得意な方はどんどん進めていっても問題ありませんが、未経験の方は上記でご紹介した答案構成の作成の練習を時間無制限で始めましょう。
この時古い過去問で練習することをおすすめします。
比較的新しい過去問や最新の対策問題は、ある程度力を身に着けてから使用する方が効率的だからです。
そして、三段論法による論述を始める際にも時間制限はせず、論述の仕方が分からない場合は参考書などを見ながら解答してOKです。
我流の書き方が癖になってしまうと、後から直すのに非常に苦労します。
最初から正しい論述法で練習していきましょう。
その後慣れてきたら時間制限を設けたり、参考書なしで学習を進めてください。
常に自分なりの意見を持ってから参考書を確認する
何度も記述していますが、論文式試験は知識をアウトプットするのではなく、論理的な思考力を試されています。
ですので、答案構成でも三段論法でも過去問でも、練習する際には自分なりの考えを持ってから、参考書や解答例を確認するようにしましょう。
そうすることで、基礎的な論述法の知識と論述内容に必要な応用力を身に着けることができます。
論文試験直前に準備すべきこと
論文式試験の前日にできるお勧め事項は以下のようになります。
- 過去問の大まかな確認
- 翌日のイメージトレーニング
- 持ち物を確認する
- 睡眠を十分とる
1は、過去問をがっつり解くというより、論点を抽出し答案構成を作成する所までを重点的に行いましょう。
当日緊張でパニックになり、論点が抽出できなければその後の作業も何も進みません。
2は当日の緊張を少しでも和らげるために行います。
自分が問題をしっかり解けている姿を想像することがポイントです。
3は、万が一の忘れ物を防ぐことや、当日の朝時間が足りなくなりあたふたしないようにするために早めに準備をしておきましょう。
最後に4番目ですが、睡眠を十分取ることも非常に重要です。
過去問を夜ギリギリまでやるのではなく、当日のひらめきや集中力に関わってきますのでないがしろにしてはいけません。
論文式試験合格を目指すならアガルート!

司法試験予備試験の論文式試験は、決まった答えを答えはなく自分で解答を作成しなくてはならず、非常に難しい試験です。
論文式試験に万全の対策をとり、最短合格を狙いたいなら通信講座のアガルートをおすすめします!
アガルートは司法試験予備試験の合格率が全国平均の4.9倍という実績を持つ、信頼と実績のある通信講座です。
論文基礎力養成カリキュラム
論文式試験にのみ対策を取りたいなら、おすすめは「論文基礎力養成カリキュラム」です。
論文基礎力養成カリキュラムは、初学者でも必要最小限の講座・時間で論文式試験に対応できる知識をえられます。
答案や演習はオンライン添削もついているため、第三者からの意見で客観的に自分の答案を見ていくことができます。
「オリジナル短答過去問集」も付属するため、短答式試験の対策にも役立てることができます。
| 論文基礎力養成カリキュラム | |
|---|---|
| 講座内容 | ・総合講義300 ・論証集の「使い方」 ・論文答案の「書き方」(オンライン添削付き) ・重要問題習得講座(オンライン添削付き) |
| 料金 | 437,800円 |
予備試験最短合格カリキュラム
論文式試験だけでなく、司法試験予備試験合格に必要な全てを学習したいならおすすめは「予備試験最短合格カリキュラム」です。
予備試験最短合格カリキュラムは法律初学者でも最短ルートで合格が目指せるよう、徹底的な合理化が測られたコスパの良いカリキュラムです。
論文式試験合格を確実なものにしたい方は、予備試験最短合格カリキュラムで学習を始めましょう!
| 予備試験最短合格カリキュラム | |
|---|---|
| 講座内容 | ・キックオフ司法試験予備試験 ・総合講義300 ・論文答案の「書き方」(オンライン添削付き) ・重要問題習得講座(オンライン添削付き) ・予備試験 論文過去問解析講座 ・旧司法試験 論文過去問解析講座 ・短答絶対合格!スキル習得講座 ・短答過去問解説講座Ⅰ(上3法) ・短答過去問解説講座Ⅱ(下4法) ・法律実務基礎科目対策講座 ・一般教養科目対策講座 ・選択科目対策講座 各科目 ・予備試験答練(オンライン添削付き) ・法律実務基礎科目答練(オンライン添削付き) ・論証集の「使い方」 |
| 料金 | 932,800円 |
司法予備試験の論文の書き方と勉強方法まとめ
今回この記事では、司法予備試験の論文式試験における論文の書き方や、勉強法などをご紹介してきました。
論文式試験は、知識をアウトプットするだけでは意味が無く、論述が非常に難しいため、予備試験の中でも難易度が高いとされています。
論文の書き方としては、基本的には三段論法で論述を行い、論述の前には答案構成を作成し全体的な流れを作っておくことが重要だとされています。
勉強方法としては、解答例を丸暗記するのではなく、常に自分の考えを持ちながら、正しい論述方法で進めていきましょう。
論文式試験は非常に難易度が高く、当日もかなり緊張することになりますが、落ち着いて冷静さを失わずに力を出し切って下さい。