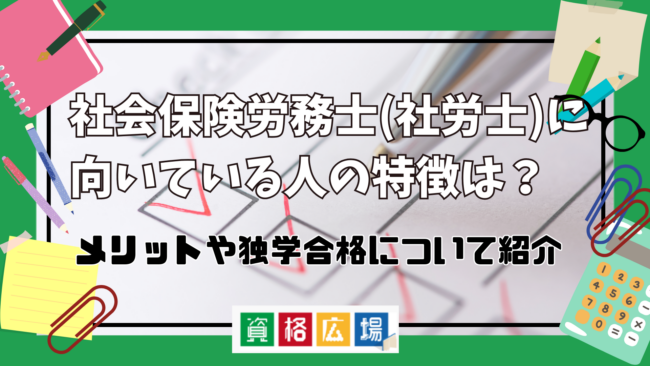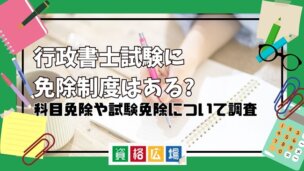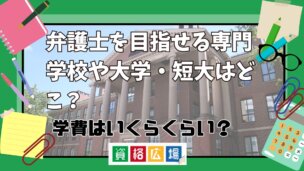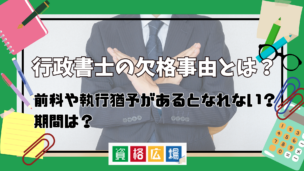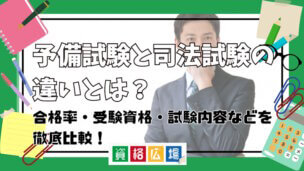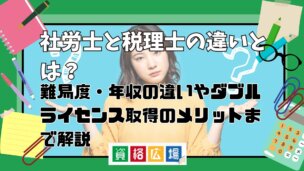難関国家資格として知られている社会保険労務士は、どんな人が向いているのでしょうか。
本記事では社会保険労務士の仕事内容や年収、働き方などを基に、社会保険労務士に向いている人や向いていない可能性がある人の特徴をご紹介します。
また、社会保険労務士として働く上で必要なスキルや就職活動をする際のポイントについても紹介します。
社会保険労務士に興味のある人や適性があるか悩んでいる人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
社会保険労務士試験におすすめの通信講座
社会保険労務士の特徴
社会保険労務士に向いている人を知るためにも、まずは社会保険労務士の特徴を確認しておきましょう。
社会保険労務士の特徴を、仕事内容・年収・働き方に分けてご紹介します。
社会保険労務士の仕事内容
社会保険労務士は、労働や社会保険関連の法律を熟知した上で、適正な労務管理や労働社会保険に関連した指導を行うことのできる専門家です。
そんな社会保険労務士の仕事内容は法律で3つに分類されています。
- 行政の機関に提出する労働・社会保険に関連した法律に基づいた申請書等の作成や、行政の機関への申請手続きの代わりをする
- 労働者を雇った場合に必要な労働者名簿・賃金台帳・出勤簿を作成する
- 労働・社会保険に関連した事項についてコンサルティングする
ちなみに1つ目と2つ目は社会保険労務士の独占業務ですので、資格を持たない人は業務ができません。
社会保険労務士の年収
社会保険労務士の平均年収は、厚労省の令和元年賃金構造基本統計調査で公開されています。
調査によると、社会保険労務士の平均年収は486万円です。
国税庁の民間給与実態統計調査では、同年度のサラリーマンの平均年収が436万円であることから、社会保険労務士はサラリーマンの平均年収より10%程度高い年収を得られることが分かります。
言い方を変えると、それだけ責任を伴う社会的価値の高い仕事と言えます。
社会保険労務士の働き方
社会保険労務士の働き方は大きく分けて2通りです。
1つ目は法人として事務所を立ち上げる独立型です。
自身の裁量が大きいため、努力すればその分高い給与を得られるのがメリットですが、契約が少なければ給与の減少に直結するのがデメリットになります。
2つ目は事務所や会社に雇われて働く勤務型です。
仕事が少ない月でも安定した給与を得ることができるのがメリットですが、給与を支払うのは会社になりますので、独立型と比べると努力が直結するとは言えない点がデメリットになります。
社会保険労務士の年収や働き方について詳細に知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
社会保険労務士に向いている人の特徴
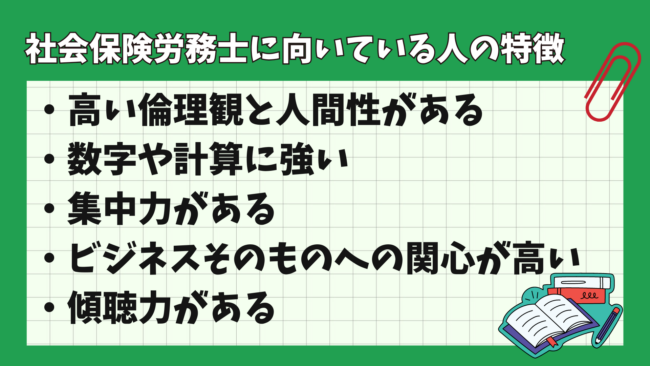
これまでの仕事内容や年収などを踏まえると、社会保険労務士に向いている人の特徴は以下のようになります。
- 高い倫理観と人間性がある
- 数字や計算に強い
- 集中力がある
- ビジネスそのものへの関心が高い
- 傾聴力がある
一つでもあてはまるなら社会保険労務士に向いています。
それぞれの特徴をもう少し詳しく見ていきましょう。
高い倫理観や人間性がある
社会保険労務士は会社や個人から労務問題について相談されたり、時には会社と労働者の間に入って仲裁したりすることもあります。
また、「残業代を出さない」「正当な給与を支払わない」などといったブラック企業に対して、労働者が本来得るべき利益を得られるように交渉もします。
これらの場面では、法律に基づいて公正に事象を判断し、思いやりや正義感をもって対応することが必要になります。
そのため、高い倫理観や人間性がある人は社会保険労務士に向いていると言えます。
数字や計算に強い
社会保険労務士の仕事は計算が必須です。
月々の健康保険料や年金支給額、労災保険料や雇用保険料など数字と向き合い、計算が必要な業務が多くあるからです。
もちろん、最近ではインターネット上で電子申請できるため、昔のように電卓片手に数字を扱う必要はありません。
それでも所属する、あるいは契約している会社の全従業員分の健康保険料や年金支給額をチェックするため、扱う数字の量は膨大です。
以上のことから、数字や計算に強い人は社会保険労務士に向いていると言えます。
集中力がある
社会保険労務士が扱う数字は、月々の健康保険料や年金支給額、労災保険料や雇用保険料などです。
これらの数字は、間違えると会社や従業員が大きな不利益を被ることになるため、集中して取り組まなければなりません。
また、これらの数字の取り扱いに加えて、多くの資料作成や書類のチェックも同時並行で進めていくこともあります。
業務の仕組みや自動計算ツールの導入などで補える部分もありますが、集中力がある人は労務士に向いていると言えます。
ビジネスへの関心が強い
社会保険労務士の仕事内容の一つに、労働・社会保険に関連した事項についてのコンサルティングがあります。
会社と従業員双方にとって一番良い労働環境を作るために時間を使うことも多くあり、社会保険労務士の独占業務ではないものの実力の見せ場でもあります。
このようなときには経営面からも事象を捉えることが必要になるため、ビジネスそのものへの関心が高い人は社会保険労務士に向いていると言えます。
傾聴力がある
社会保険労務士の元には、「ハラスメントを受けているが、どうしたら良い?」「この就業規則はおかしくないか?」など、労務管理関連で従業員が相談に来ることがあります。
労務管理関連の相談に乗る場合には、事務的に淡々と聞き取るのではなく、従業員が話しやすい雰囲気を作るために心を込めて傾聴することが求められます。
また、独立していて企業から仕事を引き受けている場合は、人事採用や評価制度についてコンサルティングをすることも多くあります。
コンサルティングの際にも、企業の制度や規模など、多くの事項を詳細に傾聴する能力が必要です。
以上のように、傾聴力は様々な場面で求められるため、傾聴力がある人は社会保険労務士に向いていると言えます。
社会保険労務士に向いていない人の特徴
社会保険労務士に向いている人の特徴があるように、社会保険労務士に向いていない人にも特徴があります。
前述した「社会保険労務士に向いている人」の裏返しの他に、以下のような特徴に全てあてはまる人は要注意です。
- 大雑把な人
- 一つの作業に集中できない人
- 本を読まない、ニュースを見ない人
- パソコンが苦手な人
それぞれの特徴を詳しく見てみましょう。
大雑把な人
社会保険労務士の仕事のうち、特に書類業務はミスの許されない仕事です。
そのため、「数字のミスがないか」「書類に不備がないか」などは、念入りにチェックする必要があります。
ですが、細部まで注意を行き届かせることなく仕事をしてしまうと、従業員や会社に多大な不利益を負わせてしまいます。
ミスが多ければ当然信用も失い、仕事もなくなって死活問題に発展するでしょう。
このような悪循環に陥りかねないため、社会保険労務士は大雑把な人には不向きと言えます。
作業に集中できない人
例えば労働保険や雇用保険などは、入社・退社・人事異動など人の流れが激しくなる年末年始や年度末に、作成・更新の手続き作業が集中します。
この時期は多忙を極めますので、特に作業に集中して取り組まなければミスに繋がりやすいです。
前述の通り、ミスは会社や従業員への不利益になりますから、大雑把な人と同様の悪循環に陥ってしまうことにもなりえます。
ですから、社会保険労務士は作業に集中できない人には不向きと言えます。
本を読まない、ニュースを見ない人
社会保険労務士の資格は、資格さえ取れば一生安泰ということはありません。
社会保険労務士として活躍するためには、労働に関する法律の変更や労働環境へのニーズの変化など、常に最先端の情報を得て業務に落とし込むことが求められます。
そのため、本を読んだりニュースに目を通したりして、自己研鑽を続けなければ他の社会保険労務士と差がついてしまいます。
ですから、社会保険労務士は本を読まない、ニュースを見ない人には不向きと言えます。
パソコンが苦手な人
社会保険労務士の主な業務である書類作成や帳簿作成の業務は、会社の規模が大きければ大きいほど、契約企業が多ければ多いほど当然増えます。
これらの業務は、パソコンが使えないことには効率よくさばくことは難しいです。
加えて、最近では従業員や企業の情報を電子管理するツールを導入するケースも多くありますから、パソコン作業がますます増えています。
そのため、社会保険労務士はパソコンが苦手な人には不向きと言えます。
社労士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
社労士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金3万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
社会保険労務士に必要なスキルを紹介
社会保険労務士に必要、またはあった方が良いスキルは以下の通りです。
- パソコン能力がある
- 情報のアップデートができる
- 営業力
- スケジュール管理能力
それぞれ項目ごとに紹介します。
パソコン能力がある
社会保険労務士の主な業務の中には、書類作成や帳簿作成、また契約企業や個人とメールでやり取りすることも多くあります。
これらの業務はパソコン能力があることで効率良く行うことができます。
具体的にはブラインドタッチができることはもちろん、エクセルやワードの基本的な操作方法が分かるなどのパソコン能力は必須と言えるでしょう。
社会保険労務士を目指すのであれば、最低限のパソコン能力は身に着けておきたいところです。
情報のアップデートができる
社会保険労務士の専門分野である労働・社会保険関連の法律は毎年のように法改正がありますので、新しい情報が次から次に出てきます。
そのため、社会保険労務士の資格を取る前だけでなく、資格を取った後も継続して勉強し、情報をアップデートすることが必要です。
社会保険労務士の資格を活かして働くなら、情報のアップデートは必須のスキルと言えます。
営業力
社会保険労務士として独立開業する場合はもちろん、事務所で働く場合にも必要なスキルが営業力です。
まず、独立開業する場合には顧客がいないことには収入がありません。
どれだけ高い専門性があったとしても、営業力がなければ顧客は得られませんので、営業力はしっかりと身に着けておきたいスキルです。
営業力があって自分で顧客開拓ができれば、事務所の売り上げに貢献できます。
売り上げに貢献できれば昇給にも繋がりやすいため、やはり身に着けておきたいスキルと言えます。
スケジュール管理能力
社会保険労務士が請け負う仕事の多くは期限があります。
加えて、社会保険労務士として認められれば認められるほど多くの仕事が舞い込んできますから、案件の数だけ期限が複数出てきます。
例えば、助成金の申請は期限を過ぎてしまえば支給してもらえませんから、数十~数百万円の損失になってしまうこともあり得ます。
そうならないためにも、社会保険労務士にとって業務のスケジュール管理は必要なスキルと言えます。
社会保険労務士の就職活動のポイント
社会保険労務士の資格を持って就職活動をする場合のポイントを紹介します。
ポイントは新卒時と転職時で大きく異なるため、2つのパターンに分けて見ていきましょう。
新卒時の就職活動のポイント
大学卒業時に社会保険労務士の資格を持っている場合は、かなり強いアピールポイントになると言えます。
企業の面接官も社会保険労務士の資格が難関資格であることは知っていることが多いですし、努力を継続して結果を出せる人というアピールにも繋がります。
ですので、大学在学時に社会保険労務士を取れたなら、それをしっかりとアピールするだけで内定をもらいやすいです。
加えて、一般企業以外にも社会保険労務士事務所や他の士業の事務所など、就職先も広がりますので良いこと尽くしです。
転職時の就職活動のポイント
社会保険労務士の資格を持って転職活動を考える場合には少し注意が必要です。
いくら難関の国家資格とはいえ、社会保険労務士の資格を持っているだけでは転職が難しいことも多いからです。
転職を考えるときに重要なポイントは2つで「実務経験があること」「+αの資格があること」です。
社会保険労務士は資格を持っていることはもちろん、実務経験があるかどうかが重要視されます。
そのため、社会保険労務士として転職を考える場合は、社会保険労務士の資格を取る前から人事部や総務などで実務経験を積んでおくことが望ましいです。
加えて社会保険労務士以外にも、ファイナンシャルプランナーや行政書士などの資格も持っておくと就職活動が円滑になるでしょう。
社会保険労務士に向いている人の特徴は?まとめ
社会保険労務士に向いている人の特徴は以下の5つでした。
- 高い倫理観と人間性がある
- 数字や計算に強い
- 集中力がある
- ビジネスそのものへの関心が高い
- 傾聴力がある
一つでもあてはまるなら、社会保険労務士の資格取得を目指すのもアリです。
社会保険労務士を目指す場合には、早期から身に着けておきたいところです。
本記事を読んで社会保険労務士への興味が深まったら、ぜひ社会保険労務士の資格取得も検討してみてください。