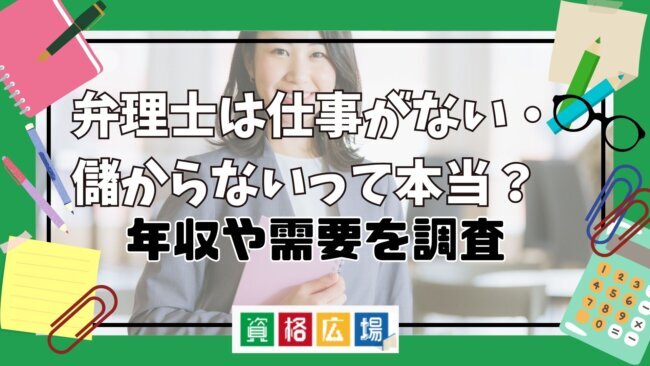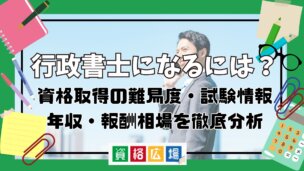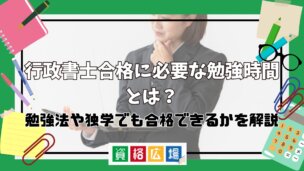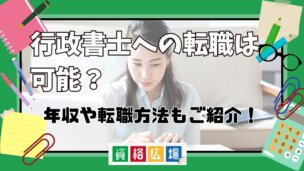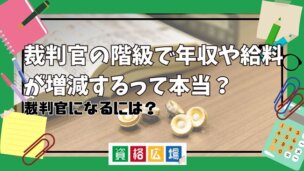弁理士は、「知的財産の専門家であり、特許、意匠、商標の出願手続き等の代理ができる資格」とされています。
また、もののデザインを保護する権利である「意匠」、商品名やサービス名を保護する権利である「商標」などの出願・権利手続きも行う仕事も担っています。
ただ、昨今において弁理士は「仕事がない」「儲からない」「割に合わない」などの言葉で検索される傾向があります。
本当に弁理士は仕事がなく、儲からず、いずれなくなる仕事なのか、年収や近年の弁理士需要の状況も含めてご紹介します。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
弁理士が「仕事がない」「割に合わない」といわれる理由は?
弁理士とは、理系資格の最高峰と呼ばれ、資格取得までに膨大な勉強量や費用がかかる職業として知られています。
また、独占業務が認められており、独立して仕事量も安定すれば、年収も日本の平均年収である473万円よりもはるかに高い年収が得られます。
では、なぜ独立業務が認められる程の国家資格で、高収入が得られる事実もあるのに、弁理士は「仕事がない」とされるのでしょうか。
弁理士の「仕事がない」と言われている理由として、以下の4点が挙げられます。
- 日本での特許出願需要が減少してきている
- 新卒弁理士には扱える仕事がない
- AIに仕事が奪われることが懸念されている
- 弁理士の人口が少なく馴染みがない
それぞれの理由を詳しくみていきましょう。
日本での特許出願需要が減少してきている
特許庁の特許行政年次報告書によれば、日本の特許出願件数は年々低下しています。
最も多かった時は2001年で439,175件の特許申請があったものの、2022年の申請件数は34.1%ほど減った289,530件となっています。
様々な原因が考えられていますが、例えば先行技術調査の精度を高めるなどして出願が厳選されるようになったことが挙げられます。
また、企業活動のグローバル化によって外国での特許出願が重要視され、その分国内での出願が減っていることも考えられるでしょう。
日本の人口減少や少子高齢化も相まって、もはや国内特許出願数は頭打ちとも言われており、今後も爆発的に回復する見込みはないと思われます。
新卒弁理士には扱える仕事がない
弁理士の資格を取得したとしても、「すぐに独立」とはいきません。
実務経験、研修、自己勉強により一人前になるための「下積み」期間が必要になります。
弁理士の仕事の花形ともいわれる「特許出願」には、豊富な実務経験が必要となります。
新卒弁理士はいくら国家試験で知識を持っているとしてもデスクワークだけでは実務経験を積むことは困難です。
そのため、資格を取り立ての新卒弁理士にとって、「特許出願」の仕事を取り扱う特許事務所(法律事務所)や企業の知的財産部門への就職はできても、新卒になって早々特許出願案件を自分一人で扱う仕事はないのです。
もちろん、下積み期間を経てようやく一人前となれば特許出願の案件を取り扱うことができますが、2~3年の下積み期間中に挫折してしまう人も多くおり、たくさんの仕事ができないまま辞めてしまうこともあります。
AIに仕事が奪われることが懸念されている
AIの技術が発達すれば、人間が行うより圧倒的にケアレスミスが減ったり、作業がスピーディーになったりして、仕事が効率的に進むことが期待できます。
弁理士の仕事である「申請書類の作成・手続き」や「先行技術調査や侵害予防調査などの各種調査」などは、将来AIに任される可能性が高いです。
弁理士のすべての業務がAIに取って代わられるということはあり得ませんが、それでも現在よりも弁理士の負担は減るため、登録者数はどんどん減る一方でしょう。
そのため、弁理士には将来性がなく、今から目指しても仕事がなかなかできなくて割に合わないと懸念されています。
弁理士の人口が少なく馴染みがない
2023年4月時点のデータによると、全国の弁理士数は11,803人で、人口10万人あたり8.47人しかいません。
弁理士の人口は非常に少ないので、日常で弁理士に出会う可能性は限りなく低いでしょう。
また、「産業財産権の取得」「発明・考案・意匠・商標に関する出願や審判請求」といった仕事内容も、一般の人には馴染みがないと感じられやすいです。
自分の身近におらず、何をしているかよく分からないので、弁理士に対して割に合わない・儲かっていないというイメージが出回っているかもしれません。
弁理士の需要は今後もあるの?
結論からいうと、弁理士の需要は現在も伸びてきており、今後もなくなる事はないといえるでしょう。
なかでも、企業からの採用や国際代理士は大幅に需要が高まっているとされています。
それぞれ詳しく理由を解説します。
企業からの採用されて活躍
日本国内での特許出願件数は頭打ちではありますが、商品の開発や研究はあらゆる企業で現在も実施され続けています。
仮にある企業がヒット商品を生み出したとしても、これに乗じて必ず他の企業が類似品を発売し始めるなどの事象が起こります。
その際、トラブルを解決するべく、弁理士事務所に依頼するのではなく、弁理士を直接雇用して対応するケースが増えてきています。
企業に雇われた弁理士の仕事は、特許に関するコンサルタントに介入しつつ、他社からの企業の知的財産権を保護しています。
以上の理由より、弁理士はコンサルタントとして企業からの需要があります。
国際弁理士として活躍
今、国内だけでなく海外において特許出願を取り扱う「国際弁理士」への需要が高まっています。
国際弁理士の仕事は、海外での「知的財産」を守ることで、PCT(特許強力条約)に加盟している155か国で活躍しています。
国際弁理士の需要が高まっている背景としては、中小企業の海外進出の増加に伴い、PCT圏内の国々で特許出願が増加してきたことが挙げられます。
また、中小企業が海外進出したにも関わらず、特許を出願していなかったことから他外国企業から商品を模倣されるなどのケースが増えたことも一つの背景として挙げられます。
ある日本国内企業の発明を海外にて特許出願したい場合、特許出願できるPCT加盟国に対して特許出願をしたり、逆に日本の特許を取りたい他国国際弁理士から特許出願の代理人オファーを受け、特許庁へ特許出願申請を行ったりします。
このように、弁理士は海外でも充分に活躍が期待できるので、まだまだ需要はあるといえるでしょう。
コンサル業務で活躍
弁理士は依頼者とのコミュニケーションが大切になる職業ですので、コンサル業務に力を入れれば需要は充分にあります。
弁理士は発明者や企業の担当者と話して、「どのような権利を取得する必要があるか」「これまでにないアイディアをどうやって言語化して申請するか」などを見定めなければなりません。
このような課題に対しては、「弁理士が依頼者の思いや意図をどれだけくみ取れるか」「親身になって寄り添えるか」が要になり、高いヒアリング力が必要です。
人間と同等のコミュニケーション能力をAIが身に付けるには、まだまだ長い時間がかかると予想されているので、コンサルに強い弁理士は将来性が高く需要があります。
書類作成などの事務作業はAIが行い、ヒアリングは人間が行うという住みわけができそうな職業ですから、弁理士の仕事が完全になくなることはないでしょう。
弁理士は儲からない?年収はどうなの?
弁理士の収入事情は、結果からいうと「ピンからキリまで」という言葉に尽きます。
以下の3点が弁理士の年収の特徴といえます。
- 平均年収は500万円~600万円
- 新卒当時の初任給は他企業の大卒と変わらない
- 経年実績次第で、1000万以上の高年収を目指せる
それぞれの特徴を解説します。
平均年収は500万円~600万円
年収のデータをあらゆる求人・転職サイトよりデータ調査したところ次のようになりました。
※以下の表は目安です。時期によって変動する可能性があります。
| 転職サイト | 平均年収 |
|---|---|
| Indeed | 497万円 |
| 転職ステーション | 582万円 |
| DODA | 628万円 |
| 求人ボックス | 573万円 |
月収については年齢や性別、給料構成におけるばらつきの差が激しく、各条件によって左右されるため比較しにくいです。
しかし、年収だけで言えば約500万~600万円が平均的な相場になります。
新卒当時の初任給は他企業の大卒と変わらない
弁理士の新卒職員の初任給は、最大大手の特許事務所でも21.5万円にとどまり、一般的な大卒の初任給と変わらない額となっています。
いくら難関資格を取得したとしても、初任給から「資格頼み」の収入は期待できません。
実務経験がない立場としては、仕方のない額ではあると思われます。
稼げるようにまでに数年ということを考えると「割に合わない」と思うかもしれませんが、おおむねどの職業でも同じように言えることですので、下積み期間は頑張って仕事をこなしていきましょう。
経年実績次第で1,000万円以上の高年収を目指せる
弁理士は下積み時代が長い職業ではあるものの、経年実績で年収は上がってくる傾向にあります。
中でも最も年収が高い弁理士の年齢層は60~64歳の年収1,405万円であり、平均年収と比較してもかなり高い収入であることがわかります。
また、独立することも年収を増やすための手法です。
独立するには、相応の仕事量やコネクション、国際特許出願ができるなど独自の付加価値を身に着けることが必要になります。
独立したことで実際に年収2,000万円~3,000万円を得ている弁理士も存在します。
独立すれば大金を稼ぐことも目指せるという夢のある職業ですので、下積み中はつらいかもしれませんが、経験値を積む期間だと割り切って乗り越えましょう。
弁理士の仕事がない・儲からない?まとめ
国内特許出願件数の減少に加え、人口が飽和化したことでさらに仕事が少なくなっていることから、弁理士には逆風が吹いている状況です。
飽和状態となっている中で仕事を獲得していくには、弁理士としての「質」を上げていかねばなりません。
ただ「弁理士の資格があるから」と慢心せず、国際弁理士になって活躍したり、コンサル業務に注力したりして、どんどん需要を高めていきましょう。
また、独立後も仕事をもらい続ければ年収が上がることは期待できるので、決して「儲からない」「割に合わない」ということはないです。
弁理士には将来性があるため、「仕事がないからやめておけ」といった周りやネットの声を気にせずに、遠慮なく目指してください!