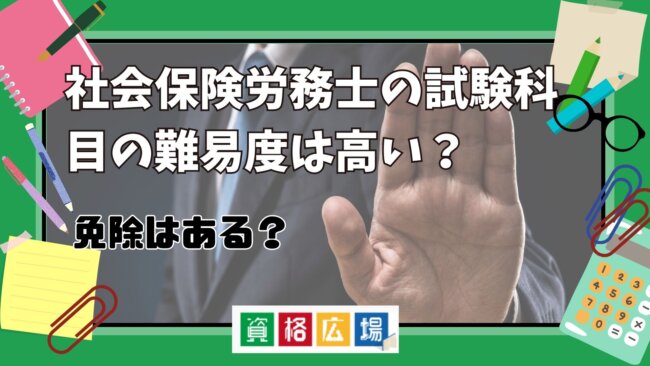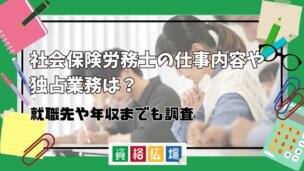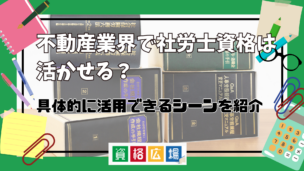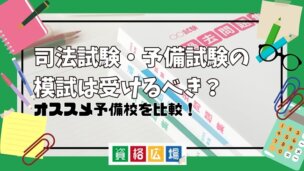社会保険労務士は労務管理のスペシャリストとして人気の高い国家資格の一つです。
取得することで就職や転職に有利になることや独立開業を目指せることから毎年多くの人が受験しています。
受験を検討される方にとって試験科目の難易度は気になるところだと思います。
この記事では社会保険労務士の試験科目の難易度や科目数、科目免除の有無などについて解説していきます。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
社会保険労務士試験におすすめの通信講座
社会保険労務士試験の試験内容・試験概要
社会保険労務士の難易度を確認する前に試験の概要について把握しておきましょう。
まずは社会保険労務士試験の出題形式や出題範囲などを解説していきます。
社会保険労務士試験概要
社会保険労務士試験は年に1回全国各地の会場で開催されます。
労務管理や社会保障に関する知識全般を問われる問題が出題され、出題形式は全問マークシート方式となっています。
問題は選択式と択一式に分かれており、選択式は40点満点・択一式は70点満点です。
社会保険労務士試験の出題範囲
出題範囲は労務管理や社会保障に関する法律で全10科目です。
労務管理に関する科目には労働基準法や労働安全衛生法、社会保障に関する科目には国民年金法、健康保険法などの科目があります。
社会保険労務士の試験科目一覧
社会保険労務士労務士試験には全部で10科目の内容が出題されると解説しました。
ここからは各科目についての詳細を解説していきます。
労働基準法・労働安全衛生法
| 出題数 | 択一式10問(労働基準法7問・労働安全衛生法3問) 選択式1問(労働基準法・労働安全衛生法併せて1問) |
|---|---|
| 配点 | 択一式10点、選択式5点 |
労働基準法と労働安全衛生法は併せて1つの項目として出題されます。
労働基準法は労働時間や賃金支払いなどに関わる労働関係の法律の基本となる科目です。
法律の条文の理解をすることはもちろんのこと、通達や判例に対する理解も求められます。
労働に関する近年の情勢も出題されるので、社会の動きもチェックしておく必要があります。
労働安全衛生法は職場の安全や衛生管理に関わる内容が出題されます。
労働基準法と比べて出題数が少ないですが、合格を目指す上ではしっかりと対策して失点を防ぐ必要があります。
労働者災害補償保険法(労働保険の徴収等に関する法律を含む)
| 出題数 | 択一式10問(労働者災害補償保険法7問・労働保険の徴収等に関する法律3問) 選択式1問(労働保険の徴収等に関する法律からの出題はなし) |
|---|---|
| 配点 | 択一式10点、選択式5点 |
労働者災害補償保険法は勤務中や通勤中に発生した怪我や病気に対して、被災労働者や遺族に保険金を給付するための法律です。
選択式は労働者災害補償保険法からの出題しかありませんが、択一式は労働保険の徴収等に関する法律からも3問出題されるので注意が必要です。
業務災害・通勤災害、業務災害に対する保険給付などの制度について一通り勉強する必要があります。
雇用保険法(労働保険の徴収等に関する法律を含む)
| 出題数 | 択一式10問(雇用保険法7問・労働保険の徴収等に関する法律3問) 選択式1問(労働保険の徴収等に関する法律からの出題はなし) |
|---|---|
| 配点 | 択一式10点、選択式5点 |
雇用保険法は失業保険の給付などを目的とした法律です。
試験範囲が広く大量の暗記を必要とする科目のため、早めに対策することが重要です。
雇用保険関係の給付金は数多くあり、制度も複雑なので一つ一つを正しく理解していきましょう。
雇用保険法も労働者災害補償保険法と同様に、択一式は労働保険の徴収等に関する法律から3問出題されます。
労務管理その他の労働に関する一般常識
| 出題数 | 択一式10問、選択式1問 |
|---|---|
| 配点 | 択一式10点、選択式5点 |
労務管理その他の労働に関する一般常識では、労務に関する最近の傾向や統計などについての知識が問われます。
また多くの法律が関わる科目なので各条文の理解が必要です。
対策が難しい科目ですが、過去問を確認して出題傾向を把握するようにしましょう。
健康保険法
| 出題数 | 択一式10問、選択式1問 |
|---|---|
| 配点 | 択一式10点、選択式5点 |
健康保険法は病気や怪我に対する保険給付に関わる法律です。
普段の生活と密接に結びついているのでなじみの深い法律ですが、制度体系はとても複雑で難易度の高い科目の一つとなっています。
苦手とする受験生も多く、時間をかけてじっくり勉強する必要のある科目と言えます。
厚生年金保険法
| 出題数 | 択一式10問、選択式1問 |
|---|---|
| 配点 | 択一式10点、選択式5点 |
厚生年金保険法は企業の従業員向けの年金に関する法律です。
法改正を繰り返していることもあり、制度が複雑でしっかりと対策を練る必要があります。
勉強する際は必ず最新の教材を使用し、法改正前の情報と混乱しないように気を付けてください。
国民年金法
| 出題数 | 択一式10問、選択式1問 |
|---|---|
| 配点 | 択一式10点、選択式5点 |
国民年金法は年金の給付に関する法律です。
複雑な厚生年金保険法と比べると比較的理解しやすい内容になっています。
得点源にしやすい科目ですので、理解しやすいからと言って勉強を疎かにせず、必ず得点できる科目にするように心がけると良いでしょう。
社会保険に関する一般常識
| 出題数 | 択一式10問、選択式1問 |
|---|---|
| 配点 | 択一式10点、選択式5点 |
労務関係の一般常識と同様に、社会保険に関する最近の傾向や統計などについての知識が問われます。
過去問から出題傾向を確認して対策を練っていきましょう。
社会保険労務士試験の合格基準点はどのくらい?
ここまで社会保険労務士の各科目について問題数や配点を確認してきました。
では社会保険労務士試験に合格するための基準点はどのくらいなのでしょうか?
ここからは社会保険労務士試験の合格基準点や採点方法について解説していきます。
社会保険労務士試験の合格基準点
社会保険労務士試験の合格基準点は厚生労働省によって下記のように定められています。
選択式試験総得点28点以上/40点、各科目5点中3点以上
択一式試験総得点49点以上/70点、各科目10点中4点以上
選択式・択一式を併せて全体では7割以上の得点で合格できるといえます。
年によって難易度にバラつきがあるため、基準点は前後することがあり、令和3年では選択式24点以上、択一式は45点以上が合格基準点となりました。
全体の得点が高くても科目ごとのボーダーラインを下回ると不合格になるので、各科目満遍なく得点を取る必要があります。
そのため、なるべく苦手科目を作らないように全体的に対策を行いましょう。
社会保険労務士試験の採点方法
社会保険労務士試験では記述試験がなく、答えをマークシートで選んでいく方式なので採点方法は正誤で判断されます。
選択式では1問の中に空欄が5つあり、一つ合っていれば1点といった方式で採点されます。
択一式では1問1点の配点で正しい答えを選べているかで採点されます。
社労士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
社労士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金3万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
社会保険労務士試験の科目別難易度は?
社会保険労務士の配点や合格基準点について解説していきました。
ここからは各科目の難易度の違いについて解説していきます。
社会保険労務士試験で最も難易度が高い科目
社会保険労務士で最も難易度が高い科目は「労務管理その他の労働に関する一般常識」と言われています。
難易度が高いと言われる要因の一つが試験範囲の広さです。
労務管理に関する30の法律が範囲に入っている上に労働経済白書の内容も問われることがあります。
対策としては過去問を繰り返し解いて、出題傾向をつかみ頻出の箇所を重点的に勉強することが効果的です。
社会保険労務士試験で最も難易度が低い科目
社会保険労務士で最も難易度が低いと言われている科目は「労働保険の徴収等に関する法律」です。
出題範囲が狭い割には、労働者災害補償保険法と雇用保険法の問題の中で計6問出題されることから得点源として活用できます。
難関の科目で失点した分は「労働保険の徴収等に関する法律」でカバーするなどの戦略を検討しましょう。
社会保険労務士試験に免除制度は存在する?
国家資格の中には実務経験などを条件に試験が免除されるものがあります。
社会保険労務士にもこのような免除制度は存在するのでしょうか?
ここからは社会保険労務士試験の免除制度について解説していきます。
社会保険労務士試験の科目免除講習
社会保険労務士試験は下記の条件を満たし所定の講習を受けると試験免除の申請を行うことができます。
- 社会保険労務士事務所の補助者で15年以上の実務経験がある者
- 健康保険組合・厚生年金基金・労働保険事務組合等の役員・従業者で15年以上の実務経験がある者
科目免除講習では労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の徴収等に関する法律、厚生年金保険法、国民年金法、一般常識の中から希望する科目を受講することができます。
1科目につき45,000円で半年間の講習や修了試験を経て受験科目が免除されます。
社会保険労務士試験の公務員実務経験者免除制度
公務員の方は実務経験があれば科目免除講習を受けずに試験免除を受けることができます。
公務員としての実務経験の内容によって免除される科目に違いがあります。
社会保険労務士試験の科目免除の条件は下記の通りです。
- 労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法に関わる実務経験が10年以上の者は労働基準法・労働安全衛生法の科目免除
- 労働保険事務の実務経験が10年以上になる者は労働保険の徴収等に関する法律の科目免除
- 国民年金法に関わる実務経験が10年以上になる者は国民年金法の科目免除
各条件に当てはまる公務員の方は申請を行うことで試験科目の免除を受けられます。
社会保険労務士試験の科目一覧と難易度まとめ
この記事では社会保険労務士の試験科目の難易度や科目数、科目免除の有無などについて解説してきました。
今回の内容のまとめは下記の通りです。
- 社会保険労務士試験は年に1回開催されマークシート式で全10科目の試験である
- 合格基準点は選択式では28点以上/40点、各科目5点中3点以上
択一式は49点以上/70点、各科目10点中4点以上 - 社会保険労務士試験で最も難易度が高い科目は「労務管理その他の労働に関する一般常識」
最も難易度が低い科目は「労働保険の徴収等に関する法律」 - 社会保険労務士試験は15年以上の実務経験があり所定の講習を受けることで一部の科目が免除されるまた公務員の場合は実務経験10年以上で実務内容によって科目免除が受けられる
この記事を参考に社会保険労務士試験合格を目指してみてください。