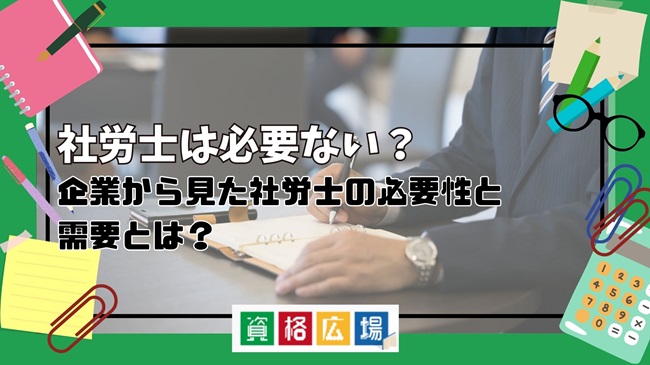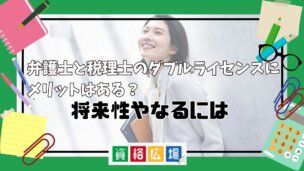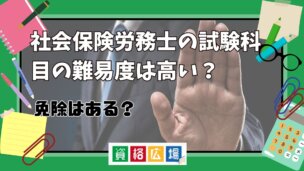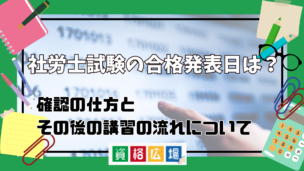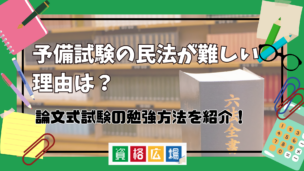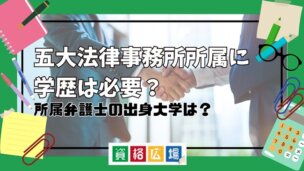ネット上にて「社労士は企業に必要ない」や、「社労士は意味ない」といったネガティブな噂があります。
そのため、社労士の資格を取得すべきかお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では「社労士が必要ないと言われる理由や、企業が社労士を雇う必要性、勤務社労士の今後の需要」について、企業側と社労士側それぞれの視点からご紹介します。
社労士を目指しているが将来性に不安がある方や、周囲に活躍している社労士がおらず不安に感じている方は、ぜひ最後までお読み下さい。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
社会保険労務士試験におすすめの通信講座
社労士が必要ないと言われる理由
冒頭でも述べたように、「社労士は企業に必要ない」という意見がネット上で見受けられます。
こちらの項目では「社労士が必要ないと言われる理由」について、以下の2つをご紹介します。
- 社労士資格がなくとも業務が遂行できるから
- わざわざ社労士を雇うコストがないから
ネガティブな噂にどのような根拠があるのか、それぞれご確認下さい。
社労士資格がなくとも業務が遂行できるため
1つ目の理由は「社労士資格がなくとも業務が遂行できるから」です。
社労士資格があることで、労働保険・社会保険に関する書類の作成方法や、就業期等の帳簿作成方法など、人事労務管理するための専門的な知識を得ることが出来ます。
ただし、作成ツールや雛形を用いることで、社労士資格がない担当者でも作成可能な書類も少なくありません。
社労士資格が無い人でも処理できる業務があるため「社労士は企業に必要ない」という意見があります。
わざわざ社労士を雇うコストがない
2つ目の理由は「わざわざ社労士を雇うコストがないから」です。
特に中小企業や設立間もない企業においては人的資金が限られているため、社労士を雇わないケースが少なくありません。
社労士を雇うコストを考慮した際に「社労士は企業に必要ない」という意見があります。
社労士の需要は年々高まっている
「社労士は必要ない」という噂に反して、企業における社労士の需要は年々高まっています。
こちらの項目では「社労士の需要が高まっている理由」について、以下の2つをご紹介します。
- 法律の強化や意識の変化のため
- 企業内でのトラブル防止など円滑な業務のため
社労士のニーズが増加している理由には、どのような背景があるのか見ていきましょう。
法律の強化や意識の変化による需要
社労士の需要が高まっている理由の1つ目として「法律の強化や意識の変化」が挙げられます。
近年働き方改革や労務意識の高まりにより、労働関係の法律が厳しくなり始め、社内で対応し切れないケースも増加しています。
また、度重なる法改正で複雑化する中で、「人事労務管理を外注する」という意識が企業において広まりつつあります。
このように法律の強化と企業における意識の変化が相まって、企業における社労士の需要が上がり続けてきました。
企業内でのトラブル防止など円滑な業務のための需要
社労士の需要が高まっている理由の2つ目は「企業内でのトラブル防止など円滑な業務を行うため」です。
社労士の仕事は企業で起こる人のトラブルを事前に防ぐために、人事・労務の管理体制を強化することです。
そのため、社労士に任せることで、人事労務上のトラブルが発生する度に社内で悩む必要がなくなり、また迅速かつ正確な提案が行われるといったメリットがあります。
企業訴訟に対するリスク管理の高まりから、企業における社労士の需要が増加傾向にあります。
社労士の業務内容からみた必要性
特定の業務に限り、社労士の必要性や需要が低いのでしょうか。
こちらの項目では「社労士の業務内容から社労士の必要性」についてご紹介します。
社労士の業務内容を1号〜3号業務に大きく分けて、順番にそれぞれの業務から社労士の必要性を解説していきます。
1号業務:書類制作と提出代行における必要性
社労士の1号業務は「労働保険及び社会保険に基づいた書類の作成と、行政機関への提出代行をする」ことです。
1号業務は電子申請化やITツール化が進む領域であるため、企業における必要性が低いと言われる傾向にあります。
しかしながら、実際は資金が限られている中小企業や、ITツールに抵抗がある企業は、社労士へ依頼するケースが一般的です。
そのため、ITツールの普及により一部の企業で需要が減る可能性は否定できませんが、完全に必要性が無くなることはないと言えます。
2号業務:保険に関する帳票の作成と就労規定の作成における必要性
社労士の2号業務は「保険に関する帳票の作成と、就労規定の作成を代行する」ことです。
企業において「労働者名簿・出勤簿・賃金台帳」という3つの帳簿作成は義務であり、また従業員10名以上の企業では就業規則の作成も義務となっています。
これらの書類は社労士資格を有しない担当者でも作成可能ですが、労働関係の法律は専門性が高いため違法となる危険性も考えられます。
社労士は2号業務を通じて企業で義務化されている書類の作成に携わることができるため、必要性が高いと言えます。
3号業務:コンサルティング業務における必要性
社労士の3号業務は「人事労務に関するコンサルティング業務」です。
先ほどもお伝えしたように、近年コロナ禍によるテレワーク環境の整備や、働き方改革による就業規則の改定など、既存の労働環境や就業規則の見直しが増え、自社内では対応し切れないことが増えました。
特に、設立間もない企業では人事労務に関する知識やノウハウが乏しく、社労士にコンサルティングを依頼するケースが増えています。
社労士は3号業務を通じて企業の労働問題を解決できるため、企業の発展に欠かせない存在と言えます。
どの業務も社労士の必要性は高い
どの業務に関して、社労士が必要ないと言われているのか詳しく業務別に見てみましたが、どの業務にも社労士は欠かせないことがわかります。
3号業務のコンサルティングは実は、社労士の独占業務ではなく資格を所持していなくとも行うことができます。
しかしながら、無資格者と資格所持者であれば資格所持者に仕事を任せたいと思うのが普通です。
徐々に、企業へのコンサルティング業務の必要性が評価されている今、社労士の仕事において役に立たない・必要ないと感じる業務はないと言えるでしょう。
社労士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
社労士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金3万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
社労士が必要となるタイミングは?
前述したように、社労士の仕事は基本的に自社内で行うことが出来ますが、第三者のプロの介入によるメリットが大きいため様々なタイミングで社労士が必要とされます。
こちらの項目では「企業において社労士が必要となるタイミング」について以下の5つをご紹介します。
- これから会社や事業を立ち上げようと考えているタイミング
- 従業員数が10名を超えるタイミング
- 事業を拡大するタイミング
- 助成金の申請を行うタイミング
- 業務が忙しくなってきたタイミング
実際企業においてどのようなニーズがあるのか、それぞれ見ていきましょう。
これから会社や事業を立ち上げようと考えているタイミング
1つ目は「これから会社や事業を立ち上げようと考えているタイミング」です。
法人を設立するタイミングで、労働保険・社会保険の新規設立に関する書類作成および加入手続きが義務となります。
会社設立には上記以外にも様々な手続きが必要となるため、経営者の多くが効率化のために社労士へ労働保険・社会保険の諸手続きを依頼します。
従業員数が10名を超えるタイミング
2つ目は「従業員数が10名を超えるタイミング」です。
従業員が10名以上在籍している場合には、労働条件等を定めた「就業規則」を作成し、労働基準管轄署に提出する義務があります。
就業規則を作成するためには人事労務の深い知識が必要となるため、社労士に依頼するケースが一般的と言えます。
事業を拡大するタイミング
3つ目は「事業を拡大するタイミング」です。
企業が事業を拡大するタイミングにて、新たに従業員を雇用する場合には労働保険等の加入手続きが必要です。
また、事業拡大に伴う労働トラブルを避けるためには、古い体制の就業規則を見直さなければなりません。
円滑に事業拡大を行う上で、人事労務に関する手続きを社労士に依頼する必要性が企業において高まります。
助成金の申請を行うタイミング
4つ目は「助成金の申請を行うタイミング」です。
助成金に関する専門知識を持たない担当者が、その都度公募要項を確かめながら申請書類を用意するのは大変手間である上に、書類の不備が発生する可能性も高くなります。
そこで、書類不備や不正受給などによる損失をなくすために、企業は社労士に助成金の申請代行を依頼します。
助成金申請は複雑化・多様化が進む領域であるため、今後も社労士の活躍分野として期待出来るでしょう。
業務が忙しくなってきたタイミング
5つ目は「業務が忙しくなってきたタイミング」です。
平常時は処理出来ていた業務も、忙しくなるのと同時に人事労務の担当者だけでは対応することが難しくなる業務も増加します。
特に、人事労務関係の法改正は毎年のように行われるため、専門外の担当者が対応するよりも社労士に依頼する方が効率的です。
そのため、担当者が対応し切れなくなるタイミングで、社労士を外注する企業や、コンサルティングを依頼する企業も多くあります。
社労士の今後の需要や将来性
社会的変化やAI技術の発展の影響を受け、社労士の存在価値は今後どのように変化するのでしょうか。
こちらの項目では「社労士の今後の需要や将来性」についてご紹介します。
これから社労士を目指す方や、将来性の高い資格職業に就きたい方は、1つずつご確認下さい。
必要性が増しており、需要が高まっている
これまでお伝えしてきたように、会社設立時から事業拡大、労働トラブルの予防など、様々なタイミングで企業に社労士が必要となることが分かりました。
また、働き方改革やコロナ禍などによる社会の変化に伴い、社労士は無くてはならない存在になっていくことが予想されます。
あらゆる企業の活動と社労士の業務内容は深い繋がりがあることから、社労士の需要は十分高く今後も需要が無くなる可能性は低いと言えます。
AIに置き換わることのない職業
職業の将来を大きく左右する「AI技術」と社労士の関係性について、1号・2号・3号それぞれの業務内容から解説していきます。
まず、1号・2号の書類作成業務に関してはパターン化が比較的容易であるため、正直AIに置き換わる可能性が考えられます。
ただし、知識や対処法については人間の深い知見が必要となる領域でありAIで実現することは難しく、入力等の単純作業が楽になるだけで完全に置き換わることはありません。
また、3号業務は高いコミュニケーション能力や提案スキルが必要であるため、会話技術が乏しいAIでは当分置き換わることはないでしょう。
このように、社労士の仕事はAIに置き換わる可能性が低いことからも将来性が期待できます。
社労士は必要ない?必要性や需要まとめ
今回「企業における社労士の必要性や、今後の需要」について解説しました。
以下のように企業の様々なタイミングで社労士が必要とされることから、社労士は企業に欠かせない存在と言えます。
| 会社に社労士が必要となるタイミング | 社労士の業務 |
|---|---|
| 会社の新規設立 | 労働・社会保険の書類作成代理 |
| 従業員数が10名を超える事業拡大 | 就業規則作成代理 |
| 助成金申請 | 助成金に関するコンサルティング申請代行 |
| 繁忙期 | 人事労務の諸手続き代理 |
また、社労士はAI技術に代替が難しい存在であることから、将来性も期待できます。
需要の高い資格職業に興味がある方は、ぜひ社労士をご検討下さい。