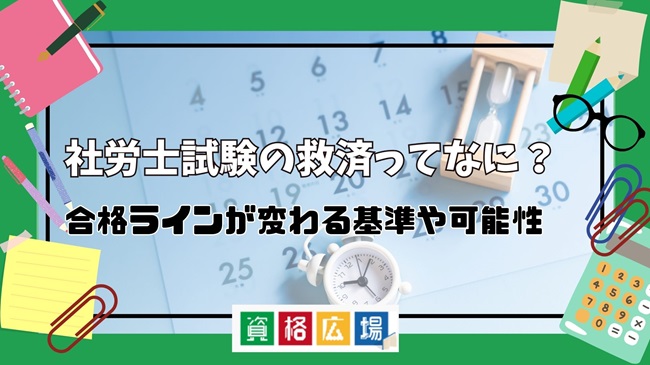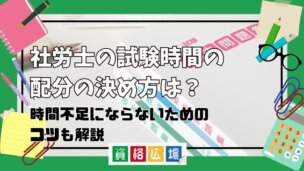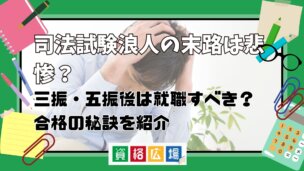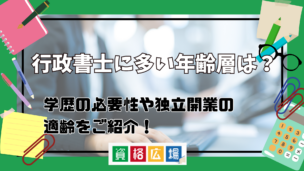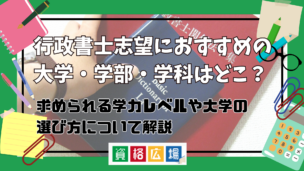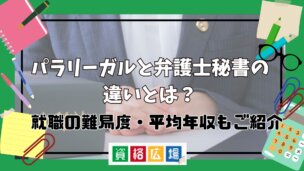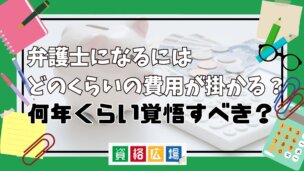社労士試験では、合格ラインを緩和する救済措置が行われることがあります。
「救済が行われたおかげで合格できた!」という声もあることから、社労士試験の受験生にとって救済は大きな関心事です。
そのため社労士試験に臨む上で、救済が行われる基準や過去の合格ラインの変動について知っておいて損することはありません。
こちらの記事では社労士試験で救済が行われる基準や過去の合格ライン、また救済が行われる可能性が高い科目について解説していきます。
社労士試験の合格を目指している方に役立つ内容となっているため、ぜひ最後までご覧ください。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
社会保険労務士試験におすすめの通信講座
社労士試験の救済とは?
社労士試験の「救済」とは「合格ラインを緩和する」措置のことです。
その年の受験者の得点を考慮し「本来の合格ラインで合否を決定した際に合格率が非常に低くなってしまう」といった場合に限り、過去の試験との難易度のバランスを保つために救済が行われます。
具体的には下記のような対応が行われます。
- 試験全体の合格基準点の引き下げ
- 科目ごとの足切り点の引き下げ
社労士試験のそもそもの合格ライン
厚生労働省によると、社労士の合格ラインは原則下記のように定められています。
- 選択式:試験総得点40点中28点以上、かつ各科目5点中3点以上
- 択一式:試験総得点70点中49点以上、かつ各科目10点中4点以上
しかし上記の合格ラインが厳格に適用されているわけではなく、年によって合格ラインが異なります。
ここで、過去の社労士試験の合格ラインを見てみましょう。
| 試験年度 | 択一式 | 選択式 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 45点以上、かつ各科目4点以上 | 総得点26点以上、かつ各科目3点以上 |
| 令和4年度 | 44点以上、かつ各科目4点以上 | 総得点27点以上、かつ各科目3点以上 |
| 令和3年度 | 45点以上、かつ各科目4点以上 | 総得点24点以上、かつ労働に関する一般常識1点以上、国民年金法2点以上、その他各科目3点以上 |
| 令和2年度 | 44点以上、かつ各科目4点以上 | 総得点25点以上、かつ労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、健康保険法2点以上、その他科目3点以上 |
| 令和元年度 | 44点以上、かつ各科目4点以上 | 総得点26点以上、かつ社会保険に関する一般常識2点以上、その他科目3点以上 |
上記を見ると、年度によって総得点に若干のバラつきがあり科目ごとの足切り基準も異なっていることが分かります。
全受験生の得点を鑑みた上で救済措置を行い、合格者数や合格率を調整しているということです。
社労士試験において救済が行われる基準
社労士試験では下記のように救済が行われる際の基準が設けられています。
- 択一式:科目における点数が3点以下の人数が受験者数の50%以上、かつ2点以下が30%以上
- 選択式:科目における点数が2点以下の人数が受験者数の50%以上、かつ1点が30%以上
つまり、救済は試験主催者のさじ加減で決まるのでは無く明確な基準に則って行われるかどうかが決まります。
受験生全体が得点できなかった科目は「例年よりも相対的に難易度が高い」ということになります。
そこで、上記の基準に該当するいわゆる「難易度が高かった場合」に必要な調整を行うことになるのです。
救済が行われる理由
救済が行われる理由は「合格者数と合格率のバランスを取るため」です。
極端に難しい年度があると社労士試験の受験者数が減少してしまい、社労士の数が減ってしまいます。
また受験年度で合格率の幅が大きいと試験の公平性や平等性が失われてしまいこちらも大きな問題になります。
つまり「試験の平等性を保ちつつ社労士の知識や技能を担保するため」にも救済措置は大きな役割を果たしていると言えます。
過去に救済が行われたのはどれくらい?可能性はある?
続いて、実際に救済が行われた試験年度について見ていきましょう。
結論からお伝えすると、社労士試験で救済が行われる可能性は高く多くの年度で救済が行われています。
実際に救済が行われた年度は?
それでは、択一式問題・選択式問題それぞれ過去5年間の救済実績を見てみましょう。
| 令和5年度 | なし |
|---|---|
| 令和4年度 | なし |
| 令和3年度 | なし |
| 令和2年度 | なし |
| 令和元年度 | なし |
| 令和5年度 | なし | |
|---|---|---|
| 令和4年度 | なし | |
| 令和3年度 | 国民年金法:2点 | 労働に関する一般常識:1点 |
| 令和2年度 | 社会保険に関する一般常識:2点 | 労働に関する一般常識:2点 |
| 令和元年度 | 社会保険に関する一般常識:2点 |
上記のように、択一式であまり救済が行われていない一方選択式では毎年のように救済が行われています。
選択式問題に苦手意識を持っている方にとっては嬉しい情報と言えるでしょう。
特に令和3年度の労働に関する一般常識に関しては足切り基準が1点以上のため、「0点の人」以外は足切りをクリアできたことになります。
ただし、令和4年度、令和5年度については択一式、選択式ともに救済はありませんでした。
救済が行われる可能性は高い!
先ほどの表を見ると分かる通り、社労士試験において救済が行われる可能性は高いです。
とはいえ救済が行われる可能性が高いのは選択式問題で、択一式問題における救済は期待できません。
また事前に救済される科目を当てることはできないため、救済をアテにせず日々の勉強に取り組んでいきましょう。
救済の対象になりやすい科目はある?
社労士試験において、救済の対象になりやすい科目は存在します。
過去のデータを見ると、以下5科目が救済対象となった年度が多いです。
- 健康保険
- 厚生年金保険法
- 国民年金法
- 社会保険に関する一般常識
- 労務管理その他労働に関する一般常識
実際上記の5科目は勉強量が多く難易度も高いことから、苦手意識を持っている方も多いのではないでしょうか?
いずれも出題範囲が広く対策が難しい科目なので、受験生全体の得点も伸びずに調整の対象となる年度が多いのです。
逆に多くの受験生が苦手としている上記科目で安定的に得点できるようになれば、合格が大きく近付くことになります。
そのため、できる限り苦手科目と苦手分野を潰しておき救済に頼らなくても足切りを回避できるレベルを目指しましょう。
苦手分野をできるだけ潰し安定して得点できるようにすることが社労士試験合格のカギです。
社労士試験講座ならアガルートアカデミーがおすすめ!
社労士試験合格を目指すならアガルートアカデミーがおすすめです!
フルカラーで見やすいテキスト教材と分かりやすい動画講義で、初めて資格勉強をする方でも充分合格が目指せるカリキュラムになっています。
合格者には受講費全額返金orお祝い金3万円の特典もあるのでモチベーションの維持も期待できます!
最短ルートで合格が目指せる!
アガルート公式HPはこちら
救済を頼らずに合格を目指すべき理由
社労士試験は1点が合否を分けることが多いため、救済の有無や救済が行われる科目によって結果の明暗が分かれます。
このように受験生に大きな影響を与える救済措置ですが、救済を頼って勉強することはおすすめしません。
下記では救済を頼るべきではない理由と勉強の心構えについて解説していきます。
不確定要素に頼るのは危険だから
社労士試験は救済が行われる可能性は高いとはいえ、救済はあくまでも例外的な措置です。
不確定要素である以上、試験後に「救済されると思っていたのに今年は救済が無かった」という事態に陥ってしまう可能性は大いにあります。
その結果1点の差で合格を逃してしまうと目も当てられないため、不確定要素である救済に頼るのは危険です。
社労士試験は難易度が高くしっかりと勉強しなければ合格できないため、救済は「行われないもの」として目の前の勉強に集中しましょう。
合格ラインギリギリを狙うのは危険だから
救済をアテにしていると合格ラインぎりぎりを狙う勉強になりがちです。
本試験ではいつもとは異なる空間で初見の問題に取り組まなければならず、心身共に消耗します。
また本番ならではの緊張感もあり、普段の実力を100%発揮できるとは限りません。
そのため、日頃から合格ラインぎりぎりの勉強をしていると「想像以上に難しかった」ということにもなりかねません。
ここでもう1度本来の社労士試験の合格ラインを確認しましょう。
- 選択式:試験総得点40点中28点以上、かつ各科目5点中3点以上
- 択一式:試験総得点70点中49点以上、かつ各科目10点中4点以上
これを踏まえ、日頃の勉強では「選択式問題は安定して32点(8割)程度取れるレベル、択一式問題は安定して56点(8割)程度取れるレベル」を目指すことをおすすめします。
合格ラインよりも上のレベルを目指すことで、精神的にも余裕が生まれるというメリットが期待できます。
勉強をサボってしまう恐れがあるから
救済をアテにしているとついつい勉強をサボってしまいがちです。
「この単元は苦手だけどみんな出来ないだろうから救済されるだろう」などと高をくくっていると、本試験で痛い目を見てしまいます。
確かに救済のおかげで合格をつかみ取れた人が存在するのは確かですが、あくまでそれは「イレギュラーな事例」です。
そのため、最初から救済をアテにして勉強の手を抜いてしまうのは本末転倒と言えるでしょう。
勉強をサボってインプットとアウトプットの質が落ちてしまうと、基本的な問題も失点するようになってしまうため注意してください。
苦手科目を放置してしまうから
前述したように、下記の科目は救済の対象となることが多いです。
- 健康保険
- 厚生年金保険法
- 国民年金法
- 社会保険に関する一般常識
- 労務管理その他労働に関する一般常識
いずれも多くの受験生を悩ませている難しい科目ですが、救済をアテにしていると気の緩みからこれらの苦手科目を放置してしまうことがあります。
社労士試験では総得点の合格ラインと科目ごとの合格ラインをクリアしなければならず、1点が非常に貴重です。
苦手科目を放置してしまうと得点が伸びない上に足切りに引っかかるリスクも高まることから、苦手科目は徹底的に潰すべきです。
苦手科目の勉強をしているとついつい逃げたくなってしまう気持ちは分かりますが、踏ん張って苦手科目を潰すように意識してください。
社労士試験の救済まとめ
社労士試験ではほぼ毎年のように救済が行われており、他の資格試験よりも救済が行われる可能性は高いと言えます。
合格ラインが緩和されることは受験生にとって非常に大きなメリットですが、普段の勉強の中では救済を意識しないようにしましょう。
救済はあくまでも「おまけ」であり、最初からアテにして勉強をしていると勉強のパフォーマンスも高まりません。
しっかりと勉強すれば着実に知識を習得できるため、日々の勉強と真剣に向き合いつつ社労士試験の合格を目指しましょう。