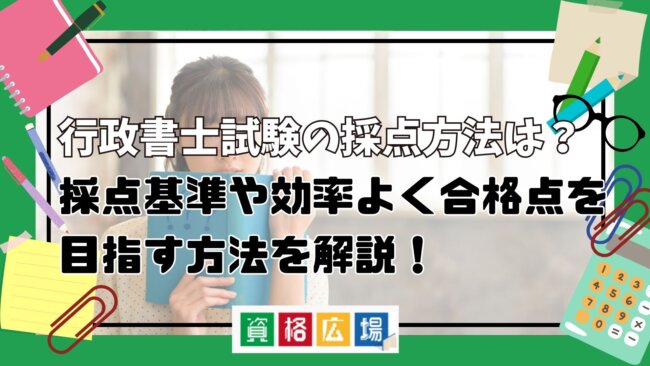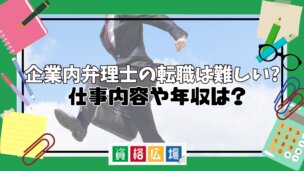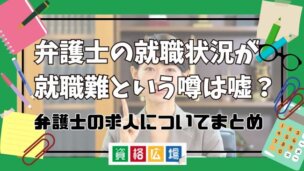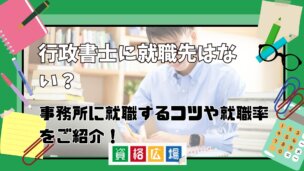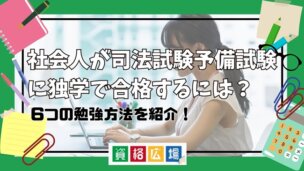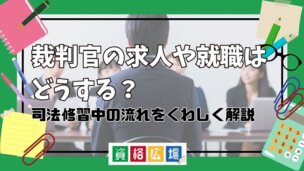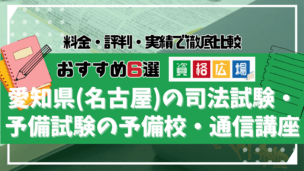行政書士試験の出題形式は、五肢択一式問題・選択式問題・記述式問題に分かれます。
いずれも採点方法と採点基準が異なるため、各問題の採点方法に合わせて最適な勉強を行うことが大切です。
採点基準を意識しつつ、各科目の進捗具合の折り合いをつけながら、効果的に勉強を進めていきましょう。
こちらの記事では、行政書士試験の採点方法や採点基準、合格点などを詳しく解説していきます。
行政書士試験の合格を目指しており、効率よく得点力を上げたいと考えている方に役立つ内容となっているので、ぜひ参考にしてください。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
行政書士試験におすすめの予備校・通信講座TOP3
行政書士試験の出題数と合格点
行政書士試験は、「法令等科目」と「一般知識科目」の2科目に大別されます。
下記の表のように、法令等科目は全46問で244点満点、一般知識科目は全14問で56点満点という内訳になっています。
| 出題数 | 配点 | |
| 五肢択一式問題 | 40問 | 160点(1問4点) |
| 多肢選択式 | 3問 | 24点(1問2点の穴埋めが12問) |
| 記述式 | 3問 | 60点(1問20点) |
| 合計 | 46問 | 244点 |
| 五肢択一式問題 | 14問 | 56点(1問4点) |
行政書士試験では法令等科目の方が圧倒的に出題のウェイトが重いため、勉強を進める過程においても法令等科目に多くの時間を割くのがセオリーです。
なお、行政書士試験の合格点は下記のようになっています。
- 法令等科目で122点以上(5割以上)得点する
- 一般知識科目で24点以上(4割以上)得点する
- 全体で180点以上(6割以上)得点する
法令等科目と一般知識科目で足切り基準が設けられていることから、「一般知識は苦手だから捨てる!」という勉強法は通用しません。
法令等科目に勉強の比重を置きつつも、一般知識も安定して4割以上の得点ができるように対策をする必要があります。
行政書士試験の出題形式と採点方法
行政書士試験は「法令等科目」と「一般知識科目」の2科目に大別されることをお伝えしましたが、「法令等科目」はさらに下記のように出題形式が分かれます。
- 五肢択一式問題
- 多肢選択式問題
- 記述式問題
それぞれ出題数と配点が異なるため、効率よく得点を稼げるように勉強する必要があります。
五肢択一式問題の採点方法(法令等科目)
まずは、1問4点で出題される法令等科目の五肢択一式問題の内訳について見てみましょう。
| 科目 | 出題数 |
|---|---|
| 基礎法学 | 2問 |
| 憲法 | 5問 |
| 行政法 | 19問 |
| 民法 | 9問 |
| 商法 | 5問 |
上記のように、行政法と民法のウェイトが重いため、行政法と民法の対策に勉強時間を割きましょう。
また、基礎法学では法律用語の基礎知識を学べるため、学習する順番は基礎法学を一番先にするのがおすすめです。
法令等科目の五肢択一式問題は160点満点で出題されますが、7~8割程度にあたる100点~120点程度の獲得を目標にすると良いでしょう。
五肢択一式問題の採点方法(一般知識科目)
次に、一般知識科目の五肢択一式問題の出題内訳を紹介していきます。
| 科目 | 出題数 |
|---|---|
| 政治・経済・社会 | 7~8問 |
| 情報通信・個人情報保護 | 3~4問 |
| 文章理解 | 3問 |
最も出題のウェイトが重いのは政治・経済・社会で、中学の「公民」や高校の「現代社会」のイメージです。
政治や国際社会に関する問題、時事に関する問題も出題されるため対策は難しいですが、足切りを避けるためにもしっかり対策しなければなりません。
情報通信・個人情報保護と文章理解に関してはそこまで難易度は高くないため、得点源にできるように対策しておきましょう。
多肢選択式問題の採点方法
続いて、多肢選択式問題の出題内訳を見ていきましょう。
なお、多肢選択式問題は3問出題されますが、各問題に4つの穴埋めがあり、1つあたり2点という配点です。
| 科目 | 出題数 |
|---|---|
| 憲法 | 1問(穴埋め4カ所) |
| 行政法 | 2問(穴埋め8カ所) |
1問で4つ穴埋めをこなしますが、1問あたり2点で採点されるため、全て分からなくても得点を稼ぐことができます。
多肢選択式は憲法と行政法から出題されますが、「五肢択一式問題」というイメージで取り組むと良いでしょう。
文章が虫食い状態になっており、語群の中から最適な選択肢を選ぶタイプの問題なので、ある程度「あたり」をつけることができます。
配点そのものは大きくありませんが、そこまで難しい出題ではないため、過去問を通じてしっかり演習をこなしておきましょう。
記述式問題の採点方法
次に、記述式問題の採点方法と出題内訳を紹介していきます。
| 科目 | 出題数 |
|---|---|
| 行政法 | 1問 |
| 民法 | 2問 |
記述式問題は、行政法から1問・民法から2問出題され、1問あたりの配点は20点です。
記述式問題では、問題文の中である事例を読んだ上で適用される法律を判断し、「どのようにするべきか」を40字程度で解答します。
法律の条文や判例、法令で定められている内容をしっかりと把握する必要があるのはもちろん、40字程度で「簡潔にまとめる」スキルも要求されます。
「記述式問題は難しいから捨てる」という受験生は少なくありませんが、全部で60点と試験全体の2割を占めることから、しっかりと対策を練りましょう。
記述式問題の採点方法は特殊
五肢択一式問題と選択式問題は、「1問4点」「1問2点」と採点方法が明確ですが、記述式問題の採点方法は明確には分かりません。
完璧に解答できていたつもりでも、20点もらえないこともあるため、記述式問題の採点方法は特殊と言えるでしょう。
苦手意識を持ちがちな記述式問題ですが、本試験対策を進める上での対策を紹介していきます。
途中点に関する採点方法は特殊
記述式問題の特徴は、「完答できなくても途中点が付与される」ことです。
残念ながら採点方法や基準は公表されていないため、明確に「どこまで解答できれば〇点」とお伝えすることはできません。
採点方法はかなり特殊ではありますが、例え自信がない問題でも「知識を総動員して回答する」ことが重要です。
「途中点が付与されたおかげで合格できた」という事例もあるため、あきらめずに取り組む意識を持ちましょう。
断片的でも構わないのでとにかく書くことが重要
記述式問題の採点方法は不明ですが、途中点がもらえる可能性がある以上、自信を持って回答できない問題でも諦めない姿勢が重要です。
完璧に解答できない問題でも、断片的でも構わないので習得した知識を総動員して「とにかく書く」ことを意識しましょう。
記述式問題は、出題の形式が大きく異なるだけで、出題内容のレベルは択一式問題や選択式問題と大差ありません。
しっかりと勉強していれば「手も足も出ない」ことはないため、苦手意識を持つことなく取り組んでみることをおすすめします。
採点方法から見た合格点到達のコツ

行政書士試験の出題形式には3種類あり、それぞれの採点方法や基準を踏まえると合格点に到達するコツが見えてきます。
効率よく、かつ着実に得点力を高められる方法を解説していくので、参考にしてください。
法令科目の対策が中心
出題数のウェイトを見ると、やはり行政書士試験に合格するためには法令等科目で確実に得点することが欠かせません。
足切りがあるとはいえ、一般知識科目の配点は56点なので、時間をかけすぎるのはコストパフォーマンスが悪いです。
イメージとしては、全体の勉強時間を「法令等科目8:一般知識科目2」程度に配分すると良いでしょう。
法令等科目の勉強が一通り終わり、安定して得点できるようになったタイミングで一般知識科目に取り組む意識で問題ありません。
民法・行政法を得点源にする
行政書士試験は、民法と行政法の出来が合否を分けます。
特に、行政法は行政書士試験の中で最も配点が高いため、行政法を得点源にできれば合格が大きく近づくでしょう。
民法も法律を初めて学ぶ人にとってはとっつきにくい箇所も多い特徴がありますが、やはり配点が高いため重点的に勉強する必要があります。
いずれも、過去問題集を何周か解き、丁寧に解説を読めば自然と理解できるようになるため、苦手意識を持っていても心配する必要はありません。
民法と行政法が得点源になれば、他の科目の出来がイマイチでも試験全体をカバーできるため、安心して試験に臨めます。
一般知識対策も必ず行う
行政書士試験では、一般知識科目も出題されます。
先述したように、一般知識科目でも足切りが設定されているため、必ず対策は行う必要があります。
法令等科目は、テキストと過去問演習を繰り返せば自然と得点力がアップしますが、一般知識は法令等科目と出題の毛色が異なるため注意しましょう。
いずれも、社会情勢や時事に関連した出題、最新の個人情報保護に関連した出題がされるため、過去問演習だけでは対応できない部分が多いです。
過去の出題傾向を把握しつつ、狙われやすい部分に関しては日頃から新聞を読むなどして対策しましょう。
記述式問題の解答に慣れておく
行政書士試験の記述式問題に苦手意識を持つ人は多いですが、解答方法に慣れてコツを掴んでおけば、本試験でも対応できます。
解答に慣れるためには、「とにかく問題に多く取り組んで、実際に書く」ことに尽きます。
実際に演習を繰り返すと「意外と大したことない」と感じられるようになるため、多くの演習をこなすことが大切です。
また、記述式問題では知識がうろ覚えだと簡潔な文章の作成ができません。
そのため、法令や条文をしっかり読み込み、正確に内容や目的を理解するように心掛けましょう。
基礎法学・商法に時間をかけすぎない
基礎法学・商法は、行政書士試験の中でも勉強の優先順位を低くして構いません。
いずれも、出題範囲が広い割には出題数が少ないため、時間をかけすぎるのはもったいないです。
過去問を見て、出題頻度が高い分野のみ勉強して、「知らない分野からの出題に関しては諦める」くらいの割り切りが大切です。
先述したように、行政書士試験の合否を分けるのは民法と行政法なので、基礎法学と商法に時間をかけるのは悪手ですので気を付けましょう。
通信講座を受講
通信講座を受講するのも、合格到達点のコツの1つです。
数ある通信講座の中でも特に人気のあるアガルートアカデミーは、2023年度の行政書士試験の合格占有率が56.11%と高い実績数を誇ります。
講師陣も全員が行政書士試験を経験しており、自身の経験をもとにして初心者でも分かりやすく面白い講座をしてくれるのも魅力の1つと言えるでしょう。
行政書士試験の採点方法まとめ
行政書士試験の採点方法や合格点などを解説してきました。
五肢択一式問題・選択式問題・記述式問題のそれぞれで採点方法が異なるため、どの科目に注力するべきか判断する材料にしてください。
行政書士試験では民法と行政法の配点が重いため、足切りに注意を払いつつ、重点的に対策すると良いでしょう。
闇雲に勉強するのではなく、重要なポイントに時間を割くことで得点力は上がるため、ぜひこちらの記事を参考にして効果的な勉強を進めてください。