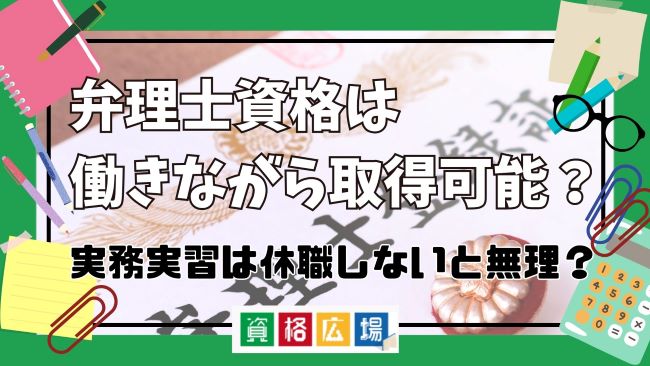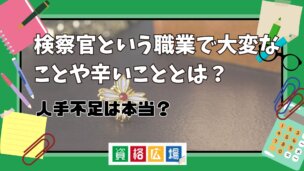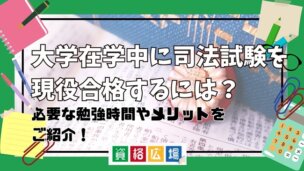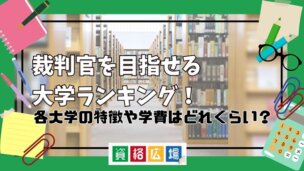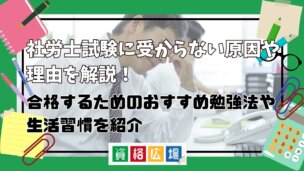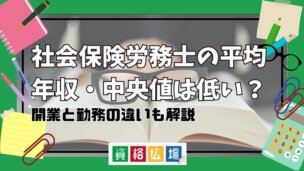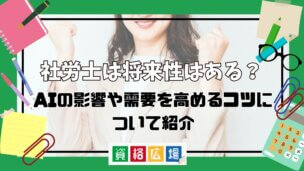弁理士は知的財産権のプロフェッショナルとして魅力があり、取得を目指す人が多い国家資格の1つです。
弁理士の資格取得を考えている方の中には、資格を取得したいけれど働きながらだと厳しいのではないかと悩んでいる方もいるかと思います。
そこでこの記事では、弁理士資格は働きながら取得することができるのかについて解説していきます。
また試験合格後の実務実習についても、休職せずに受講できるのかを確認していきます。
この記事を最後まで読めば、弁理士資格取得までの道筋を理解できるでしょう。
司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】
弁理士資格は働きながら取得可能?
結論から述べると、弁理士資格は働きながら取得することが可能です。
しかし弁理士試験の難易度は高く、働きながらだと相当な努力が必要になります。
ここではまず、弁理士試験の難易度などについて解説します。
弁理士試験の難易度と勉強時間
弁理士試験は合格率6%~9%の非常に難易度が高い試験です。
合格に必要な勉強時間は3,000時間と言われており、容易には合格できないことが分かります。
1年で3,000時間勉強しようとすると、1日あたり8時間以上勉強が必要という計算になります。
働きながら8時間の勉強時間を確保することは並大抵のことではありません。
どのくらいの期間で合格を目指すのかを考えてから計画を立てることが重要です。
働きながら合格している人もいる
働きながら弁理士資格を取得することは難しいと前述しましたが、一方働きながら弁理士資格を取得している人はいます。
実際、弁理士試験の合格者には働きながら勉強している人の方が多いそうです。
しっかりとスケジュールを立てて勉強すれば、簡単ではないにせよ働きながら試験に合格することは可能となっています。
ただし、働きながら弁理士資格を取得した人の中には3回・4回と複数回の挑戦を経て合格した人もいるのが現状です。
ある程度時間をかけながら合格するための勉強を進めていくのが良さそうです。
弁理士資格取得までの流れ

弁理士試験の難易度の高さが分かったところで、ここからは弁理士資格取得までの流れについて解説していきます。
勉強計画を立てる前に一連の流れをしっかりと把握しておきましょう。
弁理士資格取得までの流れ①1次試験
1次試験は弁理士になるにあたって1番初めに受けることになる試験です。
毎年5月に実施され、マークシートで答えを選ぶ方式となっています。
工業所有権に関する法令・工業所有権に関する条約・著作権法・不正競争防止法から問題が出題されます。
弁理士資格取得までの流れ②2次試験
2次試験は6月~8月に実施される論文式試験で、工業所有権に関する法令から出題されます。
一部例外を除いて1次試験に合格した人でなければ受験することができません。
またマークシート式から論述式へと問題形式が変わるため、1次試験とは違った形で対策が必要です。
弁理士資格取得までの流れ③3次試験
3次試験は10月に実施される口述式試験で、2次試験と同じく工業所有権に関する法令から出題されます。
免除制度もありますが、基本的には2次試験に合格することで受験資格を得られます。
3次試験では90%が合格するため、ここまで来れば合格まであともう一踏ん張りと言って良いでしょう。
弁理士資格取得までの流れ④実務実習
弁理士試験に晴れて合格した後、すぐに弁理士として登録されるわけではありません。
試験合格者は12月〜3月の間に開催される実務実習に参加する必要があります。
eラーニングや集合研修を通して弁理士になるために必要な技能の習得を目指します。
弁理士試験に働きながら合格する方法
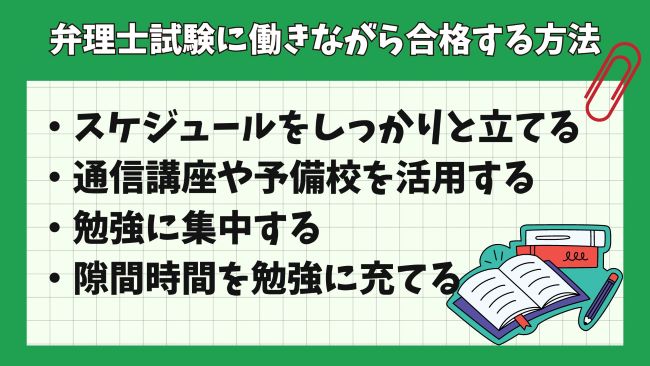
ここまで、弁理士の資格取得までの一連の流れについて見てきました。
3回の試験+実務研修と1年かけて様々な関門があり、働きながら取得できるか不安になった方も多いと思います。
ここからは、働きながら弁理士試験に合格する方法について解説していきます。
弁理士試験に働きながら合格する方法①スケジュールをしっかりと立てる
弁理士試験では合格までに必要な時間を逆算して勉強を始めることが重要です。
前述の通り、弁理士試験に合格するには3,000時間の勉強時間が必要と言われています。
1日にどのくらい勉強時間を確保できるかを考え、いつから勉強を始めるのかを計画しましょう。
また弁理士試験は1~3次試験まであるので、各試験の対策をどの配分で行うかなど計画を練ることが必要です。
弁理士試験に働きながら合格する方法②通信講座や予備校を活用する
弁理士試験は難易度が高い試験のため、独学だけでは合格が難しいと感じる方もいると思います。
その場合は通信講座や予備校を活用することがおすすめです。
独学の場合わからない部分は自分で調べるしかありませんが、通信講座や予備校の場合は講師に質問することができます。
費用はかかりますが、効率良く勉強して合格までの時間を短縮できるのであれば利用する価値は高いと言えます。
しかし予備校の場合は校舎まで通う必要があるため、時間の捻出が難しい方もいると思います。
一方通信講座であればオンラインで自宅や外出先からも受講できるため、働きながら弁理士試験合格を目指す方におすすめです。
弁理士試験に働きながら合格する方法③勉強に集中する
試験に合格するまでは遊びや飲み会の予定を入れすぎないことをおすすめします。
勉強は継続して積み重ねていくことで自分の頭に定着していくものです。
そのため「勉強する日もあればしない日もある」といった状態だとあまり効率が良くありません。
時には息抜きも必要ですが、合格まではなるべく勉強に集中することが大切です。
中途半端な勉強で試験に落ちてもう1年やり直しになるくらいなら、集中して勉強をし短期で合格する方がキャリアを考える上でプラスになります。
弁理士試験に働きながら合格する方法④隙間時間を勉強に充てる
通勤の電車の中・会社の昼休みなど、隙間時間があればそれらを全て勉強に充てることで十分な勉強時間を確保することができます。
1つ1つの時間は短くても、積み重なれば大きな勉強時間になります。
隙間時間にスマホを見るなどの習慣を辞めて、常に勉強できるように教材を携帯しておくなどといった対策がおすすめです。
弁理士資格取得のための実務実習はどんなもの?
弁理士資格取得の流れの解説の中で実務実習について触れました。
ここでは、実務実習の具体的な内容についてご紹介します。
実務実習の内容
実務実習とは、弁理士に必要な技能を身につけるために行われる研修のことです。
東京・大阪・名古屋の3都市で開催され、座学(集合研修)・eラーニングといった2通りの方法で実施されます。
実務実習は基本的に欠席が認められない上受講にあたって事前提出物があるなど、働きながら資格取得を目指す方にとってはハードな研修です。
eラーニングは講義の映像を見ながらテキストを進めていく方式で、途中に問題の出題などがあります。
正答率8割以上でないと先に進むことができないため、ただ受講すれば良いというものではありません。
事前提出課題も一定の完成度がないと受領されないため、人によっては何度も再提出を求められる場合もあります。
座学は実際に会場に行って受講する方式で5日間に渡って行われます。
日程や開催場所に縛りがあるため、住んでいる地域によっては仕事を長期間休まなければならない場合もあります。
このような実務実習の受講が無事に終了したら、晴れて弁理士として登録できるようになります。
弁理士資格取得のために休職すべき?
ここまで弁理士試験の難易度や実務実習の詳細について解説してきました。
解説を見て働きながら弁理士資格を取得するハードルの高さを感じる方もいると思います。
最後に、弁理士資格取得のために休職をするべきかどうかについて解説します。
収入に不安があるなら休職せずに一度働きながら頑張ってみる
収入に不安がある方は弁理士資格のために休職するのは避けた方が良いかもしれません。
実際、弁理士資格を取得された方の多くは働きながら資格を取得しています。
資格の取得以上に自分の生活を維持することは大切であるため、不安な場合は休職せずに働きながら資格取得に向けて頑張ってみてはいかがでしょうか。
本気で目指すなら休職や退職も視野に入れる
収入面の不安もなくとにかく本気で弁理士になりたいといった方は休職、さらには退職を視野に入れても良いでしょう。
働きながら何年も挑戦して合格を目指すなら、仕事を辞めて一定期間本気で勉強し短期で合格を目指すのも選択肢の1つです。
キャリア形成の面においても、なるべく早く資格を取得して弁理士としてのキャリアを積む方が今後の人生に有利に働きます。
「弁理士になりたい」という意思が強い方は休職や退職を検討しましょう。
働きながらひとまず試験合格だけを目指す
合格してもすぐに退職できないといった方は、ひとまず試験合格だけ目指しましょう。
弁理士の登録には期限がないため、試験さえ通っていれば実務実習のタイミングはいつでも良いとされています。
試験に合格するまでが大変なため、まずは仕事を続けながら勉強を続けていきましょう。
弁理士試験合格や実務実習は働きながらでも可能?まとめ
この記事では、弁理士資格は働きながら取得することができるのか、また実務実習は休職しなくても受講できるのかについて解説してきました。
今回の記事のまとめは下記の通りです。
- 弁理士の資格は働きながら取得は可能、しかし難易度は高い
- 弁理士試験は1次試験〜3次試験まであり、合格後は実務実習を受講する必要がある
- 働きながら弁理士の資格を取得するにはスケジュールをしっかりと立てること・予備校や通信講座を利用する・勉強に集中することなどの方法がある
- 実務実習はeラーニングと座学(集合研修)の両方を受講する必要がある
- 弁理士の資格取得のために休職・退職するべきか否かは収入に余裕があるか、なるべく短期間で取得したいかによって判断した方が良い
働きながら弁理士の資格を得ることは決して楽な道ではありません。
しかし努力した先に合格することが出来れば、知的財産権の専門家として今後のキャリアに有効に働くことでしょう。
この記事を参考に、弁理士資格の取得を目指していきましょう!